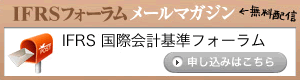連載:IFRS基準書テーマ別解説(7)
IFRSの「関連会社」「ジョイント・ベンチャー」とは
長谷川卓昭
仰星監査法人
2010/3/23
連結決算に関連するIFRS会計基準解説の2回目。IAS28号(関連会社に対する投資)については日本基準との違いを中心に、IAS31号(ジョイント・ベンチャーに対する持分)はジョイント・ベンチャーの3つの形態を中心に解説する。
PR
連結決算に関連するIFRS会計基準解説の2回目。今回は、IAS28号(関連会社に対する投資)及びIAS31号(ジョイント・ベンチャーに対する持分)についての解説である。
IAS28号は、関連会社の範囲、決算日の統一などに関して日本基準との違いを中心に、IAS31号は、ジョイント・ベンチャーの3つの形態を中心に解説していく。
【関連会社】
関連会社の範囲
関連会社(associate)とは、投資企業(パートナーシップなど法人格を持たない企業も含む)が重要な影響力(significant influence)を有し、かつ、投資企業の子会社及びジョイント・ベンチャーに該当しない企業をいう。
なお、ベンチャー・キャピタルやミューチュアル・ファンドなどが保有する特定の投資は、IAS28号の適用目的上、関連会社に該当しないとする免除規程がある。
|
重要な影響力
投資企業が、直接または子会社を通じて間接に被投資企業の議決権の20%以上を所有している場合には、当該投資企業は、重要な影響力を有していると推定される。また、議決権の所有割合が20%未満であっても、下記の事実及び状況に該当する場合には、重要な影響力を有していると判断することになる。
|
日本基準との違い
- 日本基準では、関連会社に対する持分割合を計算する際には、関連会社が他の関連会社に対して保有する持分を考慮するが、IFRSでは、投資企業の関連会社やジョイント・ベンチャーが保有する持分は、この持分割合の計算には含まれない
- IFRSでは、現時点で行使可能な転換社債やワラントなどの潜在的議決権があればその存在を考慮することになる
持分法の適用範囲
IFRSでは、連結財務諸表における関連会社に対する投資は、特定の場合を除き、持分法が適用される。持分法とは、投資を最初に原価で認識し、その後の被投資会社の純資産に対する投資企業の持分の変動に応じて、投資額を修正する会計処理方法である。
特定の場合としては、当該投資がIFRS 5号「売買目的で保有する非流動資産と廃止事業」に従って売却目的に分類される場合などがある。
日本基準との違い
- 日本基準では原則として、関連会社に加えて非連結子会社にも持分法が適用されるが、IFRSには、非連結子会社に関する定めは存在しない
- IFRSでは、日本基準に定められている持分法適用範囲に関する除外規定は定められていない
- 日本基準では子会社を有さず関連会社のみを有する場合、持分法を適用した財務諸表を作成する必要はない(投資損益の注記のみ)が、IFRSでは子会社を有しない場合にも、持分法を適用した財務諸表を作成する必要がある
実務上のポイント
- 日本基準上、影響が一時的であるとして持分法の適用対象から除外している会社がある場合には、IFRS適用に際して、当該関連会社に対する投資がIFRS5号に基づき売却目的保有に分類される要件を満たしているか否かを検討する必要がある。当該条件を満たさない場合には、持分法が適用される

 IFRS任意適用の要件緩和へ、企業会計審議会に新しい流れ
IFRS任意適用の要件緩和へ、企業会計審議会に新しい流れ