2027年までに「PoC」という言葉は使われなくなる ガートナーが提言:「上司が何も勉強せず、成果ばかりを求める例が散見される」
ガートナージャパンは、新しいテクノロジーの採用方法やエンジニアの役割変化などについての展望を発表した。エンジニアに求められるスキルや役割が歴史的な転換の時を迎えており、今後は「企画の手配師的な人ではなく、好奇心指数が高く、テクノロジーを自ら経験したり、テクノロジーの勘所を押さえられたりする人が求められる」としている。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
ガートナージャパンは2024年4月3日、新しいテクノロジーの採用方法やエンジニアの役割変化などについての展望を発表した。テクノロジーを試行的に導入する際に用いられるPoC(概念実証)の位置付けが今後変化すると同社は予測している。
「テクノロジーが使えるかどうか」ではなく「人材が使えるかどうか」へ
ガートナージャパンの亦賀忠明氏(ディスティングイッシュト バイスプレジデント アナリスト)は「『PoCによる試行導入を実施したが、それほど効果が出なかった』という話があるが、それはテクノロジーの問題というよりも人や組織のテクノロジーへの向き合い方、スキル、マインドセット、スタイルの問題が大きい」と分析。ガートナージャパンは「そうした視点が欠けているPoCをこれ以上やっても無駄」ということに気付く人が増えていくと予測している。
同社は「今後、テクノロジーが使えるかどうかを評価するためのPoCは減少し、人がそのテクノロジーを日常的に経験する機会としての試行導入へ移るだろう。企画やその試行をベンダーに丸投げしたPoCは『やった感』は出せるだけで、お金と時間を無駄にするからだ」と指摘している。
また、こうした背景から今後は「企画の手配師的な人ではなく、好奇心指数が高く、テクノロジーを自ら経験したり、テクノロジーの勘所を押さえられる人が求められる」としている。
ガートナージャパンは2027年までに日本企業の60%が「テクノロジーの試行ではテクノロジーが使えるかどうかではなく、人材が使えるかどうかが試されている」と理解し、“PoC”という言葉を廃止するとみている。
学習しない上司が増加中?
同社はリテラシーやスキルの底上げについても触れている。クラウドやAI(人工知能)などの認定資格はスキル向上に効果的だ。ガートナージャパンは「資格取得を担当者に推奨することは良い傾向だ」と評価するものの、「上司が何も勉強せず、部下にAIで成果を出すように要求するだけで、上司自身は『できるのか』『もうかるのか』といった言動を繰り返す例が散見される」と指摘する。
亦賀氏は、「IT担当者だけでなく、ビジネス/事業部門の業務担当者にも、日頃からテクノロジーを経験できる環境を整える必要がある。そして上司や役員も含めて、自らリテラシーやスキルを高めることが必要だ。さもないと、上司や役員は、現場でやっていることを評価できず、適切な指示もできない」と述べている。
関連記事
 「床で寝る」って日本の人に言ったら、びっくりされた
「床で寝る」って日本の人に言ったら、びっくりされた
グローバルに活躍するエンジニアを紹介する本連載。今回もアゼストでデータの分析や機械学習の研究などに従事する張 志穎(チョウ・シエイ)さんにお話を伺う。業務経験を積み、少しずつ日本での仕事にも慣れてきた張さんが「日本人はすごいな」と思うところとは。 宇宙ビジネスをソフトウェア開発で支える「ドメイン駆動でキャリアをつむぐ男」
宇宙ビジネスをソフトウェア開発で支える「ドメイン駆動でキャリアをつむぐ男」
本が好き。音楽が好き。でも、ドメインにコミットして複雑な仕組みを整理してソフトウェアに落とし込むことはもっと好き。 「Z世代さん」はいない――「何を考えているのか分からない」と嘆く前に
「Z世代さん」はいない――「何を考えているのか分からない」と嘆く前に
世代間ギャップに悩む管理職、リーダーの皆さん。メンバーと話をしていますか?
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

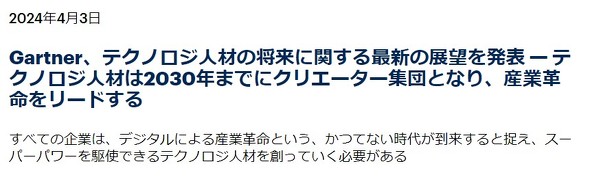 プレスリリース
プレスリリース



