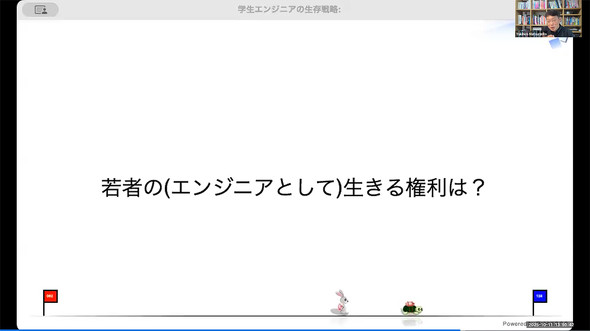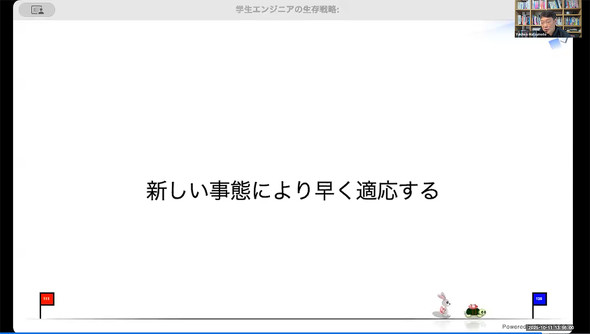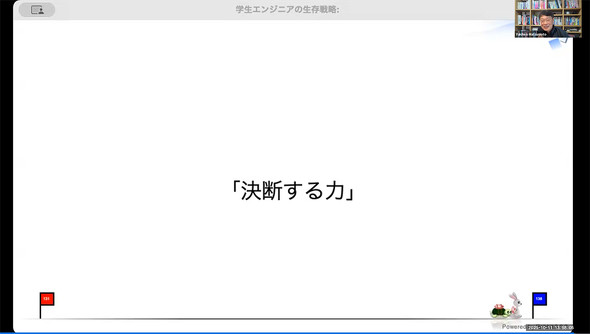Rubyの父 まつもとゆきひろさんが示す、AI時代の若いエンジニアに必要な“4つのスキル”:AIは間違えるんですよ(3/3 ページ)
AI時代の若いエンジニアに必要な“4つのスキル”
まつもとさんによると、人間とAIの架け橋になるために必要な能力は、「問題把握能力」「問題解決能力」「プログラミングスキル」「責任能力」の4つだ。
問題把握能力
問題把握能力は、課題を見つける力。AIは肉体がないので、そこからの欲求や要望がない、つまり「身体性がない」ので、「退屈」「おなかがすいた」「眠い」などの人間的な欲求を持たない。このため「何が問題かを、AI自身が自発的に発想したり、理解したりはできない。問題を見つける力は、人間固有のもの」だという。
問題解決能力
問題解決能力も同様だ。AIは解決案の選択肢を出すことはできるが、身体性がないため、どれを選べば解決につながるかを判断できない。AIから正しい解決策を引き出すのは、人間だ。
プログラミングスキル
先述のようにAIは間違えるため、人間にも正しいプログラミングスキルが求められる。従来は、「知っているかどうか」が重要だったが、AI時代は「プログラミングに詳しい人(AI)から知識を引き出す能力」が重要になるという。
責任能力
最後は責任能力だ。トラブルが起きたとき、CGで作ったAIアバターが謝っても誰も納得しない。
「下げる頭を持っているかどうかは非常に重要。頭を下げなくていいように、どういうトラブルが起きるか、それを防ぐにはどうしたらいいかを考え続けるのも、人間に求められる能力」だ。
これらの能力は、「AIがどれほど発展してもずっと必要」だし、AIは当面これらの能力は持たないであろうとまつもとさんは展望する。そして、これらの能力を鍛えるトレーニングツールとして、AIは非常に有効だという。AIから課題を出してもらい、それを解いていくことで、必要なスキルを効率的に身に付けられる。
「レジリエンス」を鍛えよ
ただ、「未来予測は基本的に外れる」ため、「AIのサポート役として、人間のエンジニアは必要であり続ける」というまつもとさん自身の予測も、外れる可能性がある。そのときに重要なのがレジリエンス(適応能力)=新しい事態に早く適応する能力だ。
社会や仕事の仕組みの変化に関心を持ち、対応して生き延びる術を考え、素早く適応し続けることこそが「メタ戦略」になる、とまつもとさんは説く。
例えば、上司から頼まれたタスクをAIに投げ、返ってきた結果をそのまま提出する。なぜこうしたのかと理由を聞かれて「AIがやりました」と答える。これでは付加価値を生み出せない。
一方、AIに適切にプロンプトを与え、間違いを修正し、コントロールして結果を出せば、そのスキルと経験が付加価値になる。右から左へデータを流すだけでなく、自分が何を付加できるかを考える。これが、AI時代のエンジニアに求められる姿勢だ。
「未来が分からない以上、何を決断しても間違える可能性はある。事前に分かる正解はない」。それでも「これが正しいはず」と決断し、責任を取る。考え続け、決断し、責任を取る――これは「人間にしかできない、人間としての能力」なのだ。
「考える力、実践する力を最大限に使って適応能力を高めることこそが、エンジニアとして未来を生き延びる生存戦略として最も重要」と、まつもと氏は結論付けた。
関連記事
 “Rubyの父”は、いかにして“つよつよ”になったか
“Rubyの父”は、いかにして“つよつよ”になったか
ハッピーになろうよ。 「競プロの神」と「Rubyの神」が考える、生成AI時代のエンジニアとプログラミング言語
「競プロの神」と「Rubyの神」が考える、生成AI時代のエンジニアとプログラミング言語
プログラミングが上達するコツは? AI時代に必要なプログラミング言語は?――2人のIT神が出会い、語り合い、共感し合った。 Rubyの父 まつもとゆきひろが就活生に贈る「失敗から学んだ7つの“格言”」
Rubyの父 まつもとゆきひろが就活生に贈る「失敗から学んだ7つの“格言”」
「名前重要」「塞翁が馬」「推測するな計測せよ」――若きエンジニアたちにまつもとさんが贈る教訓は、実用的で暖かい。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.