構造化:個別要素の重要度に着目する:「問題解決力」を高める思考スキル(5)
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
前回の記事は、「物事の全体像を見極めて構成要素を整理すること」(=構造化)について解説しました。構成要素の関係を整理したら、次はどの要素が重要なのか、どの要素なら無視しても大丈夫なのか、その「ボリューム」を素早く見分ける必要があります。それが加わることで、単に定性的に構造化した場合に比べ、問題解決の難易度や方向性が分かりやすくなります。開発現場のトラブル処理などに活用してください。
全体像を見極めてから細部に目を配る
極論すれば、あらゆる事象はすべて前回紹介したような構造図に整理できます。しかし、あまりに細かい情報を厳密に整理しようとすることは、本来の目的を考えるとむしろ逆効果になります。
なぜなら、それは複雑な事象を複雑なままとらえることになってしまい、問題解決のヒントを得にくくなったり、ささいなことに時間を費やす羽目に陥ってしまうからです。物事を構造的にとらえる意義は、本来、全体像の見通しをよくすることにありますから、その目的に立ち返り、「厳密性にこだわり過ぎることはむしろマイナス」と考えた方がいいでしょう。ある程度、ささいな部分は割り切り、全体の構造を大まかに把握することが肝要です。
さらに、全体の構造を大まかに把握した後は、どのあたりが重要なのかを見分ける必要があります。そのための最も基本的な思考スタンスが、「できる限り定量的に、ボリューム感をもって物事をとらえる」ということです。
「割り箸論争」が明らかにしたこと
定量的に状況を把握することができないと混乱を招くことがあります。例えば、かつて新聞紙上を賑わせた「割り箸論争」があります。これは、わが国独自の割り箸文化が南国の森林破壊を助長しているのではないか、というものでした。当時は常に自分の箸を持ち歩く「マイ箸」なる習慣がマスコミに多く取り上げられたりしたので、覚えている方も多いと思います。
割り箸反対派の主張は、日本で消費される割り箸は木材使用量でいえば住宅数万戸に相当する、というものでした。それだけを聞けば「大変な量だ!」と感じてしまいますが、「日本全体の木材消費量」に占める割合が小さな住宅を比較対象にしているので、相対的に大きく感じるにすぎません。
この論争は結局、「割り箸に使われている木材の量は輸入木材の全体量に比較するとコンマ数%と微々たるものである。加えて、ほかに用途のない廃材を使っているのだから、むしろ賞賛されるべきであり、森林破壊につなげるのは短絡的である」との意見が出されるに及び、議論は収束していきました。
もちろん、常に環境に配慮する姿勢は賞賛されるべきものですし、それ自体が悪いわけではありません。ただ、本来の目的に立ち返ったときに「どの部分に手を付けるのが最もインパクトが大きいか」を先に把握しておくことの重要性は分かっていただけたかと思います。
定量的に考えるメリット・デメリット
もう1つ、今度はビジネスの例を考えてみましょう。
A社の主力商品が不調なことに対して、消費者の嗜好の変化と、流通チャネルの衰退の相乗効果によるものだという定性的な分析がなされたとします。しかしこのままでは、商品改良とチャネルへのテコ入れ、どちらから手を付ければよいか分かりません。
最悪の場合、流通部門は「商品企画部門が悪い(=消費者の嗜好をとらえきれていない)」と主張し、商品企画部門は「流通部門が悪い(=チャネルを維持できていない)」と反論する……といった責任のなすり合いが行われてしまいます。
このような場合、図1のように2つの要素をある程度定量的に把握できれば、どちらの問題がよりインパクトが大きいか、どちらから着手するのが効果的か、ということがかなり明確になります。
●定量的な把握により本質が鮮明になる
このように物事を定量的にとらえることのメリットは、特に組織として動く場合に大きくなります。なぜなら、組織で動く場合には、各人の“意識のベクトル”が合っていること、そして各人の“納得度の高さ”がモチベーションに結び付いていることが重要であるからです。定量的な状況把握がしっかりしていると、「共通の指標で物事を見ることによって情報判断・解釈の個人差が減る」、あるいは「情報が伝わっていく過程で誤解される可能性が減る」ことになります。
その一方で、「数字の独り歩き」など、なまじ定量的データがあるが故に、そこで思考が停止してしまい、「本当にその定量的情報が状況を“適切に”表しているのか」を考えずに行動してしまうという現象もしばしば観察されます。冒頭の割り箸論争がよい例ですね。定量的な把握は、状況の理解を大きく助けるものの、それが絶対的真理を表すものではありません。比較対象を間違えると意思決定に大きく影響するということを常に念頭に置く必要があります。
全体を部分に分け、ビジュアルで表現する
物事を構造化し、定量的に把握する方法はいろいろありますが、最も基本となる考え方は「全体を部分(パーツ)に分け、そのボリューム感を見る」というものです。ボリューム感を見る際には、単に数字で表すのではなく、チャート化して視覚に訴えると効果的です。
●個別要素の重要度を見極める:ある家電製品のコスト構造推移
図2の例は、ある家電製品事業において、「製造」の重要度が相対的に減少し、「マーケティング」の重要度が相対的に向上した様子を、コスト構造を見ることによって示したものです。よく「製品ありきからマーケティング主導へ」といったことがいわれていますが、観念的に話をするだけでは、なんとなくしか理解できません。
それを、こんなふうに定量的に(そしてビジュアルに)表現できれば、さまざまな対策を立てたり相手を説得したりするうえで高い効果が得られるでしょう。
この「全体を部分(パーツ)に分け、そのボリューム感を見る」という作業をよりシステマチックに行うのが、コンサルティング会社でよく用いられる「モレ分析」と呼ばれる手法です。これは、全体をパーツにブレークダウンする際に、何らかの意味ある流れ・プロセスに沿って行うことで、それが「示唆するもの」や「意味合い」を引き出しやすくするものです(図3)。
●モレ分析の考え方
「モレ分析」で問題解決の難易度や方向性が分かる
応用例として、「自社のシェアをどうすれば上げられるか」という問題を考えてみましょう。顧客が自社の商品を買わない理由はいくつか考えられます。図4は、それを「顧客が商品購買に至るプロセス」という流れで切り分け、どこに根本的な原因(モレ)があるかを図示したものです。
●モレ分析の応用例(1):顧客の購買に至るプロセスを意識してモレ分析
ケースAでは、その商品を知らない顧客が多いことが問題ですから、広告投資を増加させるという手法が有効そうだと推定できます。一方、ケースBでは、知っていてそれなりに興味もあるけれど買いたいとまでは思わない顧客が多いことが問題ですから、製品仕様を改良する、あるいは顧客の認知が不十分な製品特性をもっと積極的にコミュニケーションすべく広告表現を変えたり、セールストークを変える、という手法が導き出されます。
●モレ分析の応用例(2):市場のカバー率に着目してモレ分析
図5は、同じ問題に関して、まったく視点を変えて、「市場をどれだけカバーしているか」「カバーしている範囲でどれだけの勝率を挙げているか」の流れでブレークダウンしたものです。ケースCであれば、もっと市場のカバー率を上げることが課題になるでしょうし、ケースDであれば、競合に勝つべく商品や広告やチャネル政策を変更する、あるいは値下げを行う、などの手法が必要になります。
このように、ボリューム感をもって構造的に物事を把握することで、単に定性的に見た場合に比べ、問題解決の難易度や、問題解決の方向性が分かりやすくなるのです。
筆者紹介
芳地 一也
(株)グロービス・マネジメント・バンク、コンサルタント。グロービス・マネジメント・スクールおよび企業内研修においてクリティカル・シンキングの講師も務める。東京大学文学部心理学科卒業後、(株)リクルートを経て現職。グロービスは経営(マネジメント)領域に特化し、ビジネススクール、人材紹介、企業研修、出版、ベンチャーキャピタルの5事業を展開。経営に関するヒト・チエ・カネのビジネスインフラを提供することで、日本のビジネスの「創造と変革」を目指している会社。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

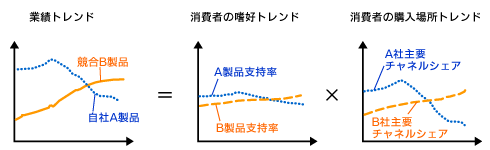 図1 定量的な把握により本質が鮮明になる。このケースでは、製品支持率とチャネルシェアを比較すると、チャネルに問題があるのが一目瞭然
図1 定量的な把握により本質が鮮明になる。このケースでは、製品支持率とチャネルシェアを比較すると、チャネルに問題があるのが一目瞭然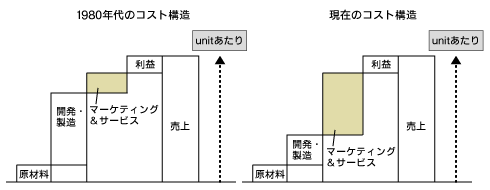 図2 構造を定量化するだけでなく、それをビジュアルで表現すると、重要度が一目瞭然となる
図2 構造を定量化するだけでなく、それをビジュアルで表現すると、重要度が一目瞭然となる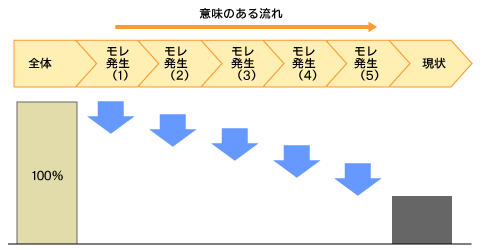 図3 全体をパーツにブレークダウンする際に、何らかの意味ある流れ・プロセスに沿って行うことで、それが示唆するものや意味合いを引き出しやすくなる
図3 全体をパーツにブレークダウンする際に、何らかの意味ある流れ・プロセスに沿って行うことで、それが示唆するものや意味合いを引き出しやすくなる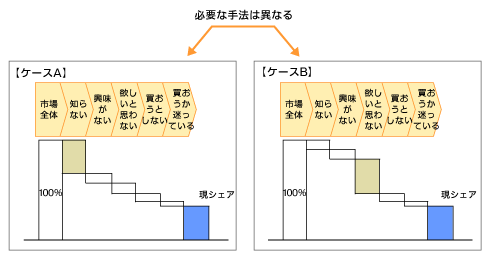 図4 システマチックに「全体」を「部分」に切り分けることで、重要なポイントが明確になる
図4 システマチックに「全体」を「部分」に切り分けることで、重要なポイントが明確になる 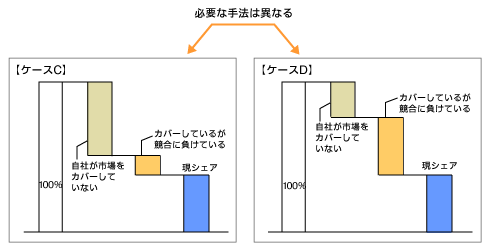 図5 モレ分析によって問題解決の難易度や方向性が見えてくる
図5 モレ分析によって問題解決の難易度や方向性が見えてくる




