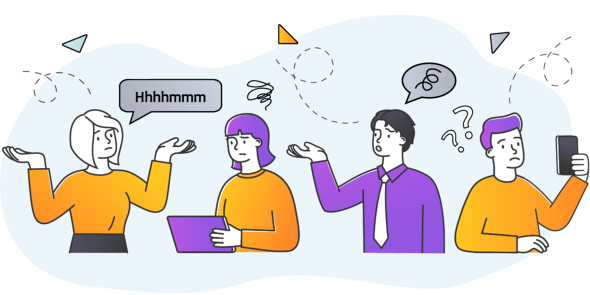「使いづらいプロダクトデザイン」はなぜ生まれるのか:プロダクト開発で見直されるデザイン(1)(1/2 ページ)
デジタルプロダクト開発に着手する企業が増える中、「デザイン」の役割が見直されている。デザイナーとエンジニアの垣根を越えた“越境開発”は企業に、そして開発の現場にどんなメリットをもたらすのか。新規事業開発に詳しいRelicのCCO(Chief Creative Officer)が解説する。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
はじめましてRelicの黒木と申します。当社は日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援しており、私はそこでCCO(Chief Creative Officer)として、事業のアイデアを魅力的に表現するための取り組みや組織開発に携わっています。本日はデジタルプロダクト(以下、プロダクト)開発におけるデザインの役割に着目し、その重要性と開発現場で必要となる取り組みについて紹介します。
開発現場で起きているデジタルプロダクトの課題
ビジネスにおいて「デジタル」(もしくはデジタル化)が重要なキーワードになっています。その理由はさまざまですが、「DX」(デジタルトランスフォーメーション)の機運の高まりと、テレワークなどコロナ禍で働く環境が変わったことが大きく影響していると考えます。Relicにも「新規事業としてプロダクト開発に取り組みたい」「既存業務のデジタル化を進めたい」という企業からの問い合わせがよくあります。規模や業種にかかわらず、あらゆる企業においてプロダクトとの接点が増加しているといえるでしょう。
ただ、こうした開発において1つの問題が起きています。
多くの人に使ってもらえるプロダクトにしようと意気込み、優秀なデザイナーを雇い、ターゲットとなるユーザーへのヒアリングを実施し、機能の導線も丁寧に設計してシンプルなデザインにした。これできっとユーザーは満足してくれるはずだと……。しかし公開してみるとユーザーが思ったような操作をしてくれない。良い評価が得られないどころかレビュー欄には「使いづらい」といった不満ばかりが並んでいる……。
なぜこういったことが起きるのでしょうか。事前のヒアリングが甘かったから? デザインがイケてなかったから? そういったこともあるかもしれませんが、著者はこの問題の原因に「当たり前」という感覚が大きく影響していると考えます。
デザインによって「当たり前」を実現することは可能なのか
プロダクトの種類によって多少の違いはありますが、多くの場合「こう操作すればこういうことができる」という“暗黙のルール”があります。メールでいえば「未読のメールはアイコンが明るい色になっており、既読にすると暗い色に変わる」、会議予約であれば「参加者全員のスケジュールの空き状況を確認でき、空いているところだけを選択できる」といった具合に。
ユーザーはそういった操作を“当たり前のこと”として認識しているもので、これが守られないと途端に使いにくさを感じてしまいます。「業務で使っていたシステムを新しいプロダクトに切り替えたら『使いづらい』と誰も使ってくれない」といった話をよく聞きますが、その原因は“慣れ親しんだ操作性からの乖離(かいり)”かもしれません。つまり、使いやすいプロダクトの条件は「これまでの当たり前をかなえていること」といえます。
ただ、ここでも問題があります。「当たり前」は、ユーザーごとに異なる文化、言語、環境など多様な前提条件が背景にあります。それらを網羅できなければ「誰が使っても当たり前に使えるプロダクト」を開発することは困難です。ではどうすればいいのでしょうか。全ての人にとっての当たり前が難しいなら、「特定の人にとっての当たり前」を実現すればいいのです。ここで2つのアプローチを紹介します。
1.「プロダクトを届けたいユーザー」を思考する
1つ目は利用するユーザーの想定シーンを考えてプロダクトを設計することです。そもそも“全ての人が使うプロダクト”を作る必要はありません。プロダクト開発には目的があり、その目的を達成したい人だけが利用できれば問題ありません。
注意点としては、ユーザーの属性を想定しただけで満足しないことです。年齢、性別、居住地など統計的な情報は大切ですが、当たり前に使ってもらうことを考える場合はユーザーの性格や価値観、行動パターンなども具体的に考えることの方が重要です。実際、こうした情報を集めるための調査や分析を実施する企業は増えており、「プロダクトを届けたいユーザーを具体的にイメージすること」の価値に多くの企業が気付き始めています。
2.「当たり前」を醸成させるデザインにする
2つ目は最初から“当たり前”を実装するのではなく、「使いながら身に付けてもらう」というアプローチです。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.