MACフレームを運ぶイーサネット物理層:進化するイーサネット(2)
この3回の連載では、イーサネットの本質と進化を分かりやすく紹介しています。第1回「『ネットワーキング』から『データリンク』提供へ」では、ブロードキャスト型のLANを起源とするイーサネットが、UTPや光ファイバを用いて全2重通信するリンク技術として高速化してきた進化の背景を解説しました。
第2回『MACフレームを運ぶイーサネット物理層』は、イーサネット物理層の進化を紹介します。パケットにヘッダとトレイラを付けたMACフレームを、どのようにUTPや光ファイバなどの伝送媒体に送出しているのかを見ていきます。イーサネットの物理層は、FDDIやファイバチャネルなど、既存の物理層技術を取り込んで次々と高速化してきました。
イーサネット物理層の特徴
IEEE標準802.3イーサネットは、隣接するルータや端末に、レイヤ3のパケットを確実に送り届けるための仕組みです。まずデータリンク層(レイヤ2)で、パケットにヘッダとトレイラを付けたMACフレームを組み立てます。次に物理層(レイヤ1)で、MACフレームを伝送媒体に適した信号波形に変換して送出します。なお、MACフレーム単位にスイッチングするIEEE標準802.1D の仕組みは、本連載では解説しません。IEEE標準802.1Dは、イーサネット専用ではなくて、IEEE標準802.11無線LANなどとのスイッチングにも同じように適用されます。
イーサネットのデータリンク層(レイヤ2)は、速度や伝送媒体の種類によらずに共通です。この共通部分に「パケットを確実に送り届ける」ための工夫が凝らされています。例えば、MACフレームのヘッダには機器固有のMACアドレスが含まれるので、間違いなく相手先に届けることができます。
また、MACフレームのヘッダとデータからCRC値を計算して、その結果を4byte長のトレイラとしてフレーム後尾に付けて送信しています。受信側でフレームの正確性を検査する手続きに利用するので、トレイラのことをFrame Check Sequence (FCS)フィールドとも呼びます。CRCはCyclic Redundancy Check (巡回冗長検査)の頭文字で、単純なパリティチェックやチェックサムよりも効率の良い誤り検出方法です。受信側で同じ計算を行ってトレイラの値と一致しなかったときには、そのフレームは自動的に廃棄されます。
つまり、伝送途中で64〜1522byte長のMACフレームに1カ所でもビット誤りが発生したら、フレームを丸ごと廃棄する仕組みになっているのです。
一方、イーサネットの物理層(レイヤ1)は、伝送速度ごとに異なります。さらに同じ伝送速度であっても、UTPや光ファイバなど伝送媒体ごとに違うのが普通です。個々の仕組みを解説する前に、まず、イーサネット物理層の役割を整理しておきましょう。
イーサネット物理層は、可変長のMACフレームを運ぶために最適化されていて、その最大の特徴はブロック符号を利用していることです。ブロック符号とは、MACフレームを、例えば4bitごとに5bit長のビットパターンに置換する符号化方法です。多少のビットレート上昇には目をつぶることで「MACフレームを運ぶ」ことに関してさまざまな恩恵が得られます。
イーサネット物理層の機能は、
- フレーム符号化(PCS:Physical Coding Sublayer 物理符号化副層)
- シリアル/パラレル変換(PMA:Physical Medium Attachment 物理媒体接続部)
- 信号波形変換(PMD:Physical Medium Dependent 物理媒体依存部)
に大別されますが、ブロック符号の恩恵はこのすべてに及びます(図1)。
受信側で説明するのが分かりやすいので、下から順に解説していきます。
信号波形変換(PMD)では、復元されるデジタル信号の「0」と「1」の個数が釣り合っていて、かつ、頻繁にビット反転していなければなりません。「0」と「1」の個数が釣り合っていれば、受信波形をアナログ増幅するときに雑音の大きい直流(DC)成分を除外できますし、デジタル信号識別(「0」か「1」かの判断)も±0を境界として簡単にできます。
また、頻繁に「0」と「1」のビット反転があれば、時間軸上のどのタイミングで「0」と「1」を判断すればよいかを決めやすくなります。ブロック符号化すると、たとえMACフレームの中身が「0」や「1」の連続であっても、常に「0」と「1」が程よく混ざったパターンに変換されます。
シリアル/パラレル変換(PMA)では、PMDで復元された受信ビット列から、符号ブロックの区切りを見つけてパラレル信号に戻す必要があります。イーサネットでは、この区切りを見つけるのに、ブロック符号化した後の特殊なビットパターンを利用しています。
例えば光ファイバを使うギガビット・イーサネットでは、インターフレームギャップ(IFG・Inter Frame Gap)に「アイドル」と呼ぶ特殊な符号ブロック(特殊符号語)を送出し続けます。この「アイドル」には、MACフレーム部分をブロック符号化したときには決して発生しない特殊なビットパターンが含まれます。
受信側では、このパターンを検出することで符号ブロックの区切りを知ることができるのです。この特殊なビットパターンは、だらだらと続くビットパターンを読みやすく区切るのに役立つので、「カンマ」(読点)と呼ばれています。
フレーム符号化(PCS)では、PMAで復元された符号ブロック列から、MACフレームを取り出す必要があります。そのためには、フレームの先頭と終端にあらかじめ目印を付けておかなければなりません。イーサネットでは、ここでもブロック符号が活躍します。フレームの先頭と終端に「特殊符号語」で目印を付けるのです。特殊符号語は、MACフレームの中身をブロック符号化するときには利用されない、特殊なビットパターンの符号ブロックです。
以下、伝送速度や伝送媒体ごとに異なるイーサネット物理層を解説していきます。
イーサネットの原点:
1芯の同軸ケーブルを使う10BASE5≫
1983年にできたIEEE標準802.3に最初から含まれる物理層規格が10BASE5(テン・ベース・ファイブ)です。「10Mbps、ベースバンド伝送、500mまで」を意味する規格名です。1芯の同軸ケーブルを使い、送信と受信を同時には行いません。CSMA/CDプロトコルを使う半2重通信だけしかできない物理層です。
なお、後から追加された、UTPケーブルを使う10Mbps規格10BASE-T(テン・ベース・ティー)も同じ符号化方法や信号変換の仕組みを使っています。こちらはツイストペア2対(4線)を使い、1対が送信専用、もう1対が受信専用なので、CSMA/CDプロトコルを使わない全2重通信もできます。
10BASE5は、MACフレームを送信しているときだけ媒体上に電気信号が存在する、バースト通信方式です。インターフレームギャップの期間は、無信号(同軸ケーブル芯線の電位がゼロ)です(図2)。
イーサネットMACフレームの先頭に8byte(64bit)長の「プリアンブル」が付いているのは、このようなバースト通信をする物理層が存在したことの名残です。「1」と「0」を31回繰り返す固定パターンで、これを受信している間に、受信機の識別レベルやタイミングを調整します。また、最後の2bitだけを「1」連続にしてあるので、その次からあて先MACアドレスが始まることが分かります。
また、10BASE5では、バースト通信の便宜を図るためにマンチェスタ符号を採用しました。マンチェスタ符号は「0」を「+1」「−1」に、「1」を「−1」「+1」に変換する方式です(図2参照)。1bitの2値(Binary)信号を2bit長の2値信号パターンに置換するので、1B/2Bブロック符号といえなくもありません(BはいずれもBinaryの略)。「1」や「0」が連続すると50ナノ秒ごとに±が反転するので、媒体上での波形変化は20Mbpsに相当します。2倍の伝送帯域が必要ですが、その代わり、完璧なDCバランスと頻繁な±反転が保証されます。
ちなみに、このようにバースト通信するイーサネット物理層は10Mbps規格だけです。100Mbps以上の普及したイーサネット規格では、IFGを特殊な符号ブロックで埋め尽くして、伝送媒体上にはフレームの有無によらず常に信号を流すようにしています(図3)。
Gbps to デスクトップ:UTPで高速化を追求
現在最も広く普及しているのが、UTPケーブルを使うイーサネット物理層です。電話の6極モジュラーコネクタを一回り大きくした、8極モジュラーコネクタ付きのLANケーブルを使います。10BASE-T(10Mbps)と100BASE-TX(100Mbps)では、ケーブル内のツイストペア2対(4線)を1対ずつ送信および受信専用に使います。これに対して、1000BASE-T(1Gbps)は、ツイストペア4対(8線)すべてを送受信に共用します。
これら速度の異なる3種類の物理層は、まったく異なる符号化方法を採用しているので互換性がなく、同じ種類でないと通信できません。そのため、IEEE標準802.3にはオートネゴシエーション(自動折衝)という機能があります。UTPケーブルをつないだときや機器に電源が入った際に、自分が動作可能な規格をお互いに相手に伝え合うプロトコルと、そのときに使う共通の符号化方法を定めています。
どの物理層規格を使うかお互いで相談してから、合意できた物理層規格でリンクアップする仕組みです。お互いが共通に複数の物理層規格をサポートしている場合には、より性能の高い方を選ぶ約束になっています。最近では、単一のLSIチップが、10BASE-Tと100BASE-TXの2種類、あるいは1000BASE-Tを含めた3種類すべての物理層機能を内蔵する例が増えています。
10BASE-T規格は、1990年にIEEE標準802.3に追加されました(補追規格802.3i)。リピータハブを中心に半径100mまでのスター状配線が可能です。符号化や信号変換の方法は、すでに紹介した10BASE5と同じです。マンチェスタ符号を使って媒体上でもバースト通信する、イーサネットの原点ともいえるオリジナルな符号化方式を継承しています。
100Mbpsの物理層規格100BASE-TXがIEEE標準802.3に追加されたのは1995年です(補追規格802.3u)。FDDIの物理層規格を借用して、一気に10倍の高速化を達成しました。FDDIはトークンリング型の100Mbps光LAN規格です。1980年代後半から1990年代前半にかけて、その高速性(!)から、構内網バックボーンに利用されていました。光LANとして出発したFDDIでしたが、低コスト化を図る目的で、UTPケーブル用のFDDI物理層が後に追加されました。
100BASE-TXは、10BASE-Tと同じく、ツイストペア2対(4線)を送信と受信でそれぞれ1対ずつ専有します。10倍の伝送速度で同じ100mの到達距離を保証できるのは、以下の改良を施しているからです(かっこ内は10BASE-T)。
- 周波数特性の良いカテゴリ5のUTPケーブル(⇔カテゴリ3)
- 符号化効率の良い4B/5B符号(⇔1B/2B符号)
- 波形変化の少ない3値信号MLT-3(⇔2値信号NRZ)
- IFGに特殊符号を送出し続ける連続通信方式(⇔バースト通信方式)
カテゴリ5のUTPケーブルは、現在、最も普及しているLANケーブルです。10BASE-T規格が想定したカテゴリ3は、構内の電話配線に利用される細めのケーブルです。「ボイスグレード」と呼ばれることもあります。
100BASE-TX規格が採用した4B/5B符号は、4bitの2値(Binary)信号を、5bit長のパターンに置換するブロック符号です。5bit長のパターンは32通りありますが、そのうち、「0」が3つ以上は連続しない「素性の良い」パターン16通りを、4bitの2値信号(16通り)に1対1に対応させています。また、この16通りのパターン以外に、数通りのパターンを特殊符号語として利用します。IFGアイドルや、MACフレームの先頭や終端の目印になります。
実際のツイストペアに電位差変化として送出するときには、4B/5B符号化されたデジタルビット列を、スクランブラでランダマイズしてから、3値信号MLT-3に変換しています(図4)。ランダマイズ(スクランブル)するのは、MACフレームがなくてIFGアイドルを連続送信し続ける場合などに、短い周期で繰り返すビットパターンによって電磁誘導輻射(EMI: Electro Magnetic Interference)が発生して、周囲に悪影響を及ぼすことを避けるためです。100BASE-TXのスクランブラは、bit列に対して2047bit周期の疑似ランダム固定パターンとの排他的論理和(EXOR)を取る方式です。
こうしてbit列を「かき混ぜ」てから、3値信号MLT-3に変換します。MLT-3変換(Multi-Level Transmission - 3)は、2値のデジタル信号「1」「0」を、「+1」「±0」「−1」の3値信号に変換する方式の一種です。デジタル信号が「1」のたびに、「+1」→「±0」→「−1」→「±0」→「+1」に順次変化させ、「0」のときには出力を変化させません(図4)。
10BASE-Tと100BASE-TXの一番の違いは(4)「連続通信方式」の導入かもしれません。100Mbps規格は、同軸ケーブルでの半2重通信は想定せず、送信と受信にそれぞれ専用のツイストペア1対を使います。技術的に複雑なバースト送受信を行う必要がないので、MACフレームを送信しないインターフレームギャップの期間には、特殊な5B符号ブロック「11111」を送出し続ける連続通信方式になりました。
なお、100mのUTPケーブルで1Gbps伝送が可能な1000BASE-T物理層がIEEE標準802.3に追加されたのは、1999年のことです(補追規格802.3ab)。ツイストペア4対(8線)を使い、さらにエコーキャンセラの力を借りて、同じツイストペア上で双方向の同時連続通信を実現しています(図5)。
この1000BASE-T規格のために、8bitの2値(Binary)信号を5値(Quinary)信号4組に変換する新しいブロック符号8B/1Q4が開発されました。この4組の5値信号を、4対のツイストペアで同時送信します。28(=256)通りのデータを、54(=625)通りの符号ブロックにマッピングするのです。この結果、個々の波形変化の最短周期を100BASE-TXと同じ8ナノ秒に保ったまま、100mのギガビットUTP伝送が実現されています。
身近になったイーサネット光物理層
ギガビット・イーサネットの登場は、LANに光ファイバが普及する契機になりました。光ファイバは伝送帯域が広く、ギガビット級の速い波形変化もゆがむことなく遠くまで伝搬させるので、モールス信号のような発光/消光(2値信号)で通信できます。これに対して、UTPケーブルを使う1000BASE-Tには、エコーキャンセラやゆがみ補正など、高度なデジタル信号処理技術が必要で、標準化および市場に製品が登場するまでに時間を要しました。
また、最近ではFTTHサービスが始まり、光ファイバを使う100Mbpsイーサネット技術も身近になってきました。以下、光ファイバを使うイーサネット物理層の進化を紹介します。
100Mbps光物理層100BASE-FXは、1995年にIEEE標準802.3に追加されました(補追規格802.3u)。光を導く「コア」部分が太く接続やコネクタ加工が容易な2芯マルチモード光ファイバ(MMF)を伝送媒体に使います(〜2km)。UTPを使う100BASE-TXと同じく、100Mbps光リング規格FDDIの物理層をほぼそのまま借用した規格です。MACフレームやIFGを4B/5B符号化してから、そのシリアルビットパターン(連続信号)をNRZI(Non Return to Zero Inversion)光変換します。「1」で発光/消光を切り替え、「0」では何も変化させない変換方式です(図6)。
UTPを使う100BASE-TX(図4)とは異なり、スクランブラが要りません。光ファイバなら、IFGなどで繰り返しビットパターンが生じても、伝送媒体から妨害電波が発生しないからです。また、単純な2値信号として光変換するのは、光ファイバの伝送帯域が十分に確保できるからです。多値変換をして、信号変化の基本周期を長くする必要がありません。
100Mbpsのイーサネット物理層がFDDI技術を借用したのに対して、光ファイバを使うギガビット・イーサネット1000BASE-SX/LXは、ファイバチャネル規格の物理層技術を流用しました。ファイバチャネルは、SCSIなどのパラレル・バス・インターフェイスに代わるシリアル・チャネル・インターフェイスとして、ホストコンピュータと大規模ハードディスクアレイなどを接続するために1990年代前半に開発された規格です。ギガビット級の光通信技術を、低コストのコンピュータ系インターフェイスに採用したパイオニア(先駆者)です。
1000BASE-SX/LXがIEEE標準802.3に追加されたのは1998年です(補追規格802.3z)。SXはMMFを使う規格で、ファイバ性能にもよりますが、220〜550mは届きます。CDプレーヤなどと同じ波長帯(0.8μm)の、コストの安い表面発光型半導体レーザを利用します。
これに対してLXは、屋外光通信網で普及しているシングルモード光ファイバ(SMF)を使う規格で、少なくとも5kmまで届きます。SMFは「コア」部分が細くて伝送帯域が広いので、ギガビット級の速い波形変化でも、ゆがみが少なく遠方まで届けることができます。光通信用の、波長1.3μmの端面発光型半導体レーザを利用しています。
これら光ファイバを使うギガビット・イーサネットは、ファイバチャネル規格に沿って8B/10B符号とNRZ光変換方式を採用しています。MACフレームやIFGを8bitごとに10ビットパターンに変換したシリアルビットストリームを生成し、単純に、「1」で発光、「0」で消光させます(図7)。
8B/10B符号は、5B/6B符号と3B/4B符号を組み合わせたユニークなブロック符号です。4B/5B符号と同じ25%のビットレート上昇ながら、完璧なDCバランス、多数の特殊符号、カンマの存在など、機能が格段に充実していて、まさに「MACフレームの伝送に最適なブロック符号」です(参考文献の付録「Ethernetにおける符号化技術の発展」参照)。
アクセスを目指すイーサネット(EFM)
ギガビット・イーサネットがLANで普及したのに対して、光ファイバを使う100MbpsイーサネットはFTTHで脚光を浴びています。ただし、現時点では、IEEE標準802.3の物理層としては、2芯のMMFを使う100BASE-FX規格しかありません。このために、UTPを使う100BASE-TX規格からFTTH用にカスタマイズされた伝送媒体(メディア)に変換するメディアコンバータが利用されています。FTTHでは1芯SMFを使う例が多く、波長多重技術を用いて1芯で双方向の同時通信を実現します。4B/5B符号化やNRZI光変換は、すでに紹介した100BASE-FX規格(図6)をそのまま利用します。
現在、IEEE標準委員会802では、FTTHなどのアクセスネットワークに適用する物理層をIEEE標準802.3(イーサネット)に追加する審議が進んでいます。このために、EFM (Ethernet in the First Mile)と呼ばれるタスクフォース(分科会)802.3ahが組織されています。そこでは、1芯SMF以外にも、DSL技術を流用して電話線1対2線を使う物理層や、光分岐のあるPON(Passive Optical Network)を伝送媒体に使う物理層の追加が検討されています(図8)。
例えば、1芯SMFを使う100Mbps 物理層規格は100BASE-BX10と呼ばれる見込みです。波長多重技術を使うので、1.3μm帯を送信に使う物理層と、1.5μm帯を送信に使う物理層とを対向させる必要があります。この2種類のPMDを区別するために、規格名の末尾にUもしくはDをつけます。Upstream(上り)もしくはDownstream(下り)の頭文字です。
【参考文献】
「10ギガビットEthernet教科書」IDGジャパン(著者と日立電線 瀬戸康一郎氏の共同監修)
ここまでで、さまざまなイーサネット物理層の仕組みがご理解いただけましたでしょうか? 第3回は、新しい適用領域SAN/WANを目指すイーサネットの進化に焦点を当て、その特徴を紹介します。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
編集部からのお知らせ

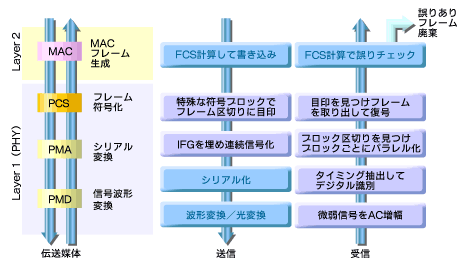 図1 イーサネット物理層におけるブロック符号の役割
図1 イーサネット物理層におけるブロック符号の役割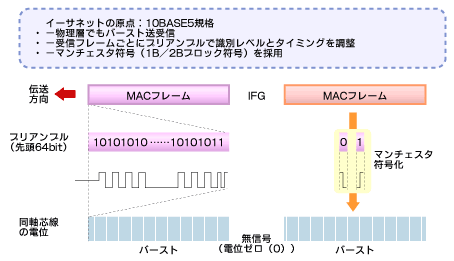 図2 10BASE5規格の特徴
図2 10BASE5規格の特徴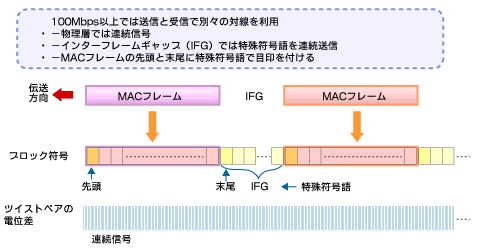 図3 100Mbps以上のイーサネット物理層
図3 100Mbps以上のイーサネット物理層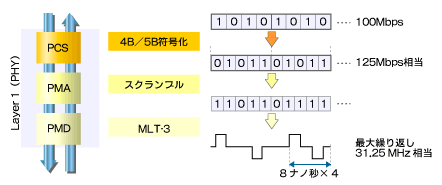 図4 100BASE-TXの出力
図4 100BASE-TXの出力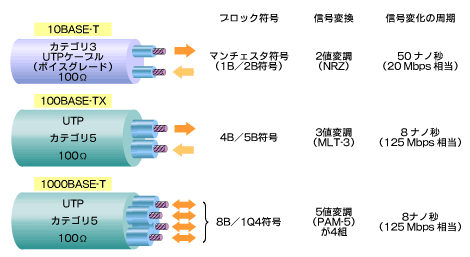 図5 10/100/1000BASE-T物理層の比較
図5 10/100/1000BASE-T物理層の比較 図6 100BASE-FXの出力
図6 100BASE-FXの出力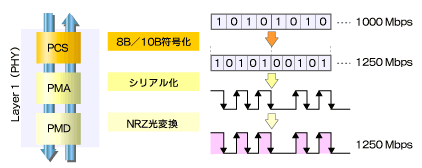 図7 1000BASE-SXや1000BASE-LXの符号化方式
図7 1000BASE-SXや1000BASE-LXの符号化方式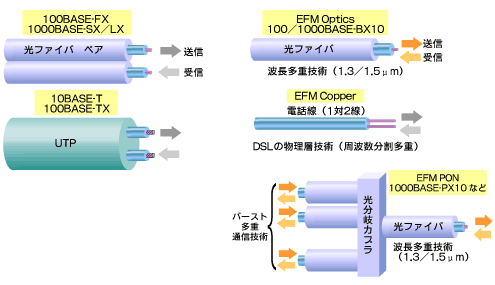 図8 Ethernet in the First Mile(EFM)の物理層(審議中)(左側は従来例)
図8 Ethernet in the First Mile(EFM)の物理層(審議中)(左側は従来例)



