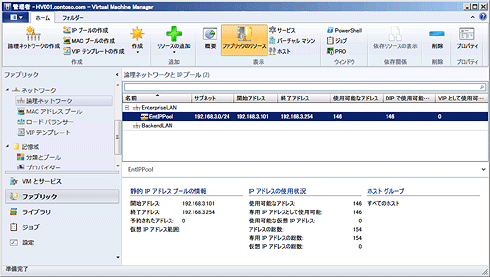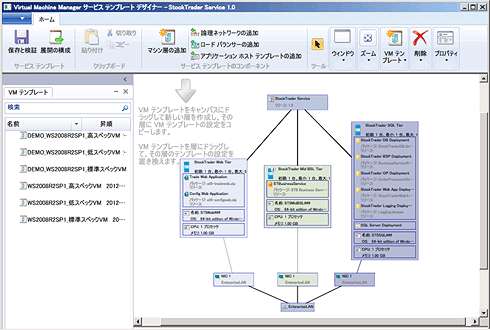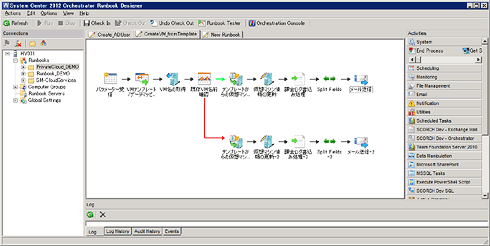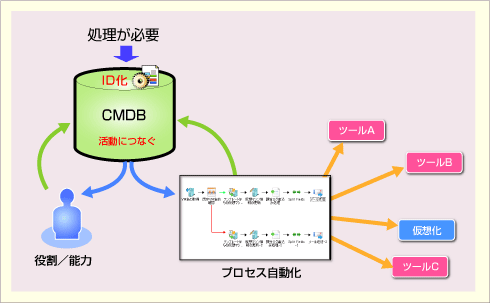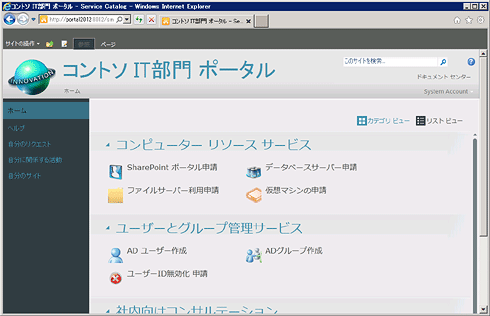第1回 System Center 2012の概要:一から知るSystem Center 2012と仮想化管理 Virtual Machine Manager(2/2 ページ)
各コンポーネントの紹介 〜データセンター管理というシナリオ〜
System Center 2012の最も大きなターゲットは、企業のデータセンターの発展形といえるプライベート・クラウドである。ただ、この言葉は受け取る人によってイメージが異なるため、ここでは「仮想化や自動化技術を活用した効率的なシステム運用の実現」と捉えていただければよい。それに対してSystem Center 2012が何を実現しようとしているかを、下図に表してみた。伝えたいことはこの図に盛り込まれている。
【仮想化という基盤の管理: Virtual Machine Manager(VMM)】
注目度の高い仮想化は、これからもIT基盤にとって重要な位置を占めることだろう。System Center 2012の中でも仮想化の管理は中心的な機能の1つだ。ただ、仮想マシンを自動的に作るだけなら、OS標準のスクリプトでもできてしまう時代である。運用管理ツールを導入するメリットとしては、仮想化基盤構築に必要となる物理マシンやストレージ、ネットワークまでも管理できる点が挙げられるだろう。ほかにも、System Center 2012では、アプリケーションの仮想化支援まで行うことも可能だ。
【仮想化を含むシステムの自動化推進: Orchestrator】
一時期、仮想化=自動化と勘違いをしてしまうケースが見受けられた。しかし、仮想化することで可能になる自動化は、ITシステムの中ではごく一部でしかなく、最近では仮想化を包含した自動化を目指す動きが出てきた。「ランブック(Runbook)オートメーション」と呼ばれる、運用プロセスそのものを自動化しようという取り組みである。このランブックを実現するには、複数のツールをまたいだ、さまざまな処理を自動的に処理する必要があり、その動きから「オーケストレーション(Orchestration)」と呼ばれることもある。これからのデータセンターは、物理環境も仮想環境もアプリケーションも、Active Directoryの処理も含め、それぞれの専用管理ツールを使うのではなく、ランブックで定義されたプロセスの中で自動処理がなされるようになっていくだろう。
【今こそ稼働監視が重要に: Operations Manager(OM)】
正しい自動化は、正しい監視から生まれるといっても過言ではない。システムの今の状況を正しく把握できているからこそ、いま何を処理するかが分かるからだ。System Center 2012の中で稼働監視を担う「Operations Manager(OM)」は、これまで着実に監視対象を広げてきた。現在は、Windows ServerやSQL Serverといったマイクロソフト製品だけでなく、各メーカーから提供される物理マシンや、UNIXやLinuxなどのOSのサービス監視、高価な専用ツールが使われることの多いネットワーク機器監視なども標準機能として実現している。さらにSystem Center 2012からは、Javaや.NETのアプリケーションのレスポンスやパフォーマンスの監視も始めており、プログラムの不具合個所の特定まで自動的に行えるようになった。アプリケーションは作って終わりではなく、稼働し始めてからの方が長く周りに影響を及ぼすため、アプリケーション監視はシステム運用の中で重要な要素になっていくだろう。
| 種別 | 監視可能な製品/サービス | |
|---|---|---|
| マイクロソフトの製品/サービス | Windows Server、SQL Server、Exchange Serverなど | |
| Windows Azure | ||
| UNIX/Linux | IBM AIX 7.1(Power) | |
| HP-UX 11i v2 IA64 | ||
| HP-UX 11i v2 PA-RISC | ||
| HP-UX 11i v3 IA64 | ||
| HP-UX 11i v3 PA-RISC | ||
| Red Hat Enterprise Linux ES Release 4 | ||
| Red Hat Enterprise Linux Server release 5.1(Tikanga) | ||
| Red Hat Enterprise Linux Server release 6 | ||
| Solaris 9 SPARC | ||
| Solaris 10 SPARC | ||
| Solaris 10 x86 | ||
| Solaris UTF-8 Support | ||
| SUSE Linux Enterprise Server 9(i586) | ||
| SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1(i586) | ||
| SUSE Linux Enterprise Server 11(i586) | ||
| アプリケーション・サーバ | Windows Server .NET Framework | |
| WebSphere | ||
| WebLogic | ||
| JBOSS | ||
| Tomcat | ||
| ネットワーク機器 | 800以上のネットワーク機器をサポート | |
| 物理マシン | 各メーカーのサーバ・ハードウェアを監視可能 | |
OMは、マイクロソフト製品以外にもUNIXやLinux、Javaアプリケーション・サーバに800以上のネットワーク機器まで監視できる。
【結局はITILというサービス管理: Service Manager(SM)】
想像してほしい。運用管理の現場が、ツールの進化によって少しずつ自動化に向かうのは間違いない。しかし、自動化を手放しで喜んでばかりもいられない。なぜなら、その自動的な処理がうまく実行されているかどうかの判断ができなければ、正しい運用とはいえないからだ。そこで登場するのが、数年前まで運用のベスト・プラクティスだともてはやされたITILである(ITILの詳細は関連記事を参照)。システム上で実行されるさまざまな処理の履歴は、「CMDB(構成管理データベース)」というデータベースに記録され、運用におけるさまざまなリスクへの対応もCMDBが中心となって行われることになる。
それでは、System Center 2012におけるサービス管理とこれまでのITILとの違いは何か? それは、ランブックとの連動である。例えば、インシデントが1つ発行されたとすると、これまでは人をアサインして、手動で処理が行われ、手動でインシデントがクローズされていた。しかし、これではCMDBにデータは集約されるものの、現場の担当者の手間が増えてしまう。そこで、これからはインシデントに対してランブックをアサインできるようにする。もちろん、ランブックで自動処理が成功したか失敗したかもCMDBに残ることになる。
どんなに自動化が進もうと、結局、管理はなくならない、ということでもある。
【迅速な復旧を意識したデータ保護: Data Protection Manager(DPM)】
簡単にいえば、「Data Protection Manager(DPM)」はバックアップの機能である。ただ、データをバックアップしておくことに加えて迅速に復元できることが重要だという認識から、DPMはテープではなくディスクにバックアップを取る方法を採用している。保持しているデータも常に復元しやすい形に成形するという特長を持つ。またIT基盤で動作するシステムのデータ保護に必須の機能として、SQL ServerやExchange Serverといったアプリケーションのデータを意識したバックアップや、Hyper-Vベースの仮想マシンのバックアップにも対応している。
【セルフサービスの推進が運用の迅速化とコスト削減に】
企業ではこれまで数年かけて仮想化を進めてきたわけだが、同じようなテクノロジを使っているにも関わらずパブリックなクラウドの進化は目覚ましいものがある。企業システムにおいては、クラウドを使えば楽になるという単純な話で済まないことも多いのは事実である。それでも、せっかく先進のお手本があるのだから、それを利用しない手はない。その1つがセルフサービス(ITのサービス化)という考え方である。
エンドユーザーからの要求を受け取って、IT担当者が決まりきった処理をするのであれば、受け取った要求を基に自動的に処理ができるような仕組みを作ればよいだけなのだ。まったく新しいことをするのではなく、不要なプロセスを削減しようというだけだ。System Center 2012には、セルフサービス用のポータルが用意されているため、仮想マシンを作るのも、Active Directoryのユーザー操作やパスワード・リセットも、SharePoint Serverに部門やプロジェクト専用のポータルを作るのも、すべてセルフサービス化できるというわけだ。セルフサービスからの申し込みもすべて、CMDBに登録されるとしたら、それはもともと実現したかったITILの延長といえる。このようにITのサービス化とは、特別なことではなく、本来やるべきことだと気付いていただければ幸いである。
今回は、System Center 2012が持つシナリオとして、PCやデバイスの管理、そして仮想化→自動化(稼働監視)→ITサービス管理→セルフサービス化という流れについて見てきた。そもそもシステム管理で実現したかった目的(あるいは問題の解決)のために、常に大きな視野を持つことのメリットを感じていただければ幸いである。
なお、System Center 2012を試用したい場合は、次のページから評価版を入手できる。
- System Center 2012とオプションのWindows Server 2008 R2 SP1のダウンロード(マイクロソフト TechNet)
さて、次回から2回にわたり、System Center 2012の中核機能でもある仮想化の管理に特化して、解説していく。
関連リンク
- System Center 2012の製品情報ページ(マイクロソフト)
- System Centerテクニカル・リソース(マイクロソフトTechNet)
- System Center 2012評価版のダウンロード・ページ(マイクロソフトTechNet)
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.

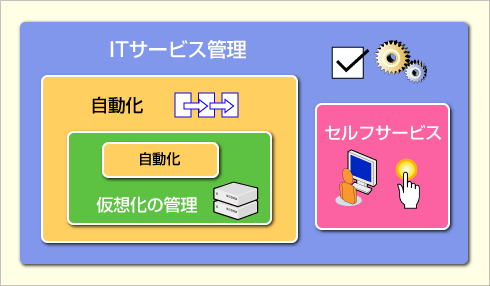 System Center 2012が実現しようとしていること
System Center 2012が実現しようとしていること