IBMとIDC Japanが語るワークスタイル変革の現在と未来とは:IBM Connect Japan 2016
日本アイ・ビー・エムは2016年7月27日、東京・お茶の水のソラシティカンファレンスセンターで『「IBM Connect Japan 2016」〜新しい働き方へ導く「次の一手」』を開催。IDC Japanによる基調講演が行われた。
日本アイ・ビー・エムは2016年7月27日、東京・お茶の水のソラシティカンファレンスセンターで『「IBM Connect Japan 2016」〜新しい働き方へ導く「次の一手」』を開催した。
冒頭、あいさつに立った日本アイ・ビー・エム ソーシャル事業部理事 事業部長 田崎慎氏は次のように述べた。
「日本で少子高齢化が進む中、ホワイトカラーの生産性の低さが問題となっている。先進諸国の中では日本のホワイトカラーの生産性は最下位。本日は、この問題に対して、コラボレーションというソリューションを使って、具体的にどのような解決策を示せるのかをご紹介したい。IBMはVerseという新しいインタフェースを持ったコラボレーション・ソリューションを2015年に、市場投入し、好評をいただいている。これまでのメールボックス中心から『人を中心に、仕事を中心に』という考え方で、圧倒的に生産性を上げるツールとなっている。
パートナー連携ではApple、Twitterに続きBox、Cisco Systemsとの戦略協業を発表しており、コラボレーション領域でもお客さまのニーズに沿ったより、優れたインテグレーションを実装できるようになった」
さらに田崎氏は「自然言語に対応し、学習するコンピューティングであるコグニティブ」について触れる。「IBMが最も注力している分野であり、コラボレーションツールの中にその機能の実装を開始しており、さらに生産性を圧倒的に向上すると期待されている。また、Notes/Dominoは25周年となり、お客さまの中に大量のデータが蓄積されている。このデータをコグニティブに投入して、従来、ある業務にしか使えなかったデータを、新しい企業価値に変え、ダークデータに光を与えていくことができないかと検討している」とした。
あらためて「コグニティブ」とは何か、コグニティブサービスがどのような形で提供されているのか
続いて同社 常務執行役員 コグニティブ・ソリューション事業担当の松永達也氏が「IBM コグニティブ・ビジネスのご紹介」と題して、オープニングスピーチを行った。
松永氏は、IBM Watsonについてビデオを通じて紹介した後、「コグニティブという用語は日本語にしにくいが、英語だと、Get to know =分かるようになる、理解するようになるといった意味。人間が考え、学習する一部を、人間のパートナーであるWatsonが支援する。当初、Watsonは医療分野の研究、ゲノム解析、膨大な資料の読解などに使われた。スピード感が特徴で、ディープラーニングだと根拠が分からないが、Watsonは根拠を明らかにして推論、レコメンドするため、ビジネスに活用できる」と解説した。
「ダークデータ、非構造化データは企業の中に自然言語で書かれた資料、センサーデータ、音声、画像、SNSデータなど大量に存在するが、これらを対象に推論し、学習するのがWatsonだ。さまざまな場面で実用段階に入ってきた。2016年2月に日本語化サービスを開始し、9月には東京でWatsonのデータセンターがオープン。2016年後半にかけてWatsonの活用がより具体化する。既に活用されている分野を見ると、金融業界でのコールセンターでの利用が進み、顧客の対応時間が10%削減されたケースも出ている。かんぽ生命様では年間200万件の金融のアドバイザー機能、意思決定や保険の支払・適用審査業務に対応している。製造部門では技術系サポートに活用されている」。
また、コグニティブサービスがどのような形で提供されているのかについて松永氏は、「一番下の知識ベースが重要。この中にさまざまなデータを蓄積していく。例えば、NotesのデータをWatsonで活用することにより、新しいデータの活用の仕方が生まれてくるのではと期待している。コグニティブサービスでは130ほどのAPIが、PaaSであるBluemix上に載っており、Watsonをクラウドサービスで手軽に利用できるようになる」とし、コグニティブサービスの分野として「コールセンターやWebマーケティングなどの新しい顧客体験、治療法などの新しい発見、自分自身が好きなワインの選定などの他、画像認識など右脳のサポート始まっている」とした。
また松永氏は、これらの事業の進め方としてエコシステムについて解説。「開発パートナーとして100社、8万人の開発者、大学との連携も100件実現している。言語も日本語含め、8カ国語に対応している。さらに、ハッカソンも開催しており、先般のハッカソンでは弁護士ドットコムさんが優勝された」と披歴した。
IDC Japanが提唱するワークスタイル変革の現在と未来
続いての基調講演「ワークスタイル変革の現在と未来 〜クラウド、モバイル、コグニティブシステムが働き方を変える」では、IDC Japan リサーチ第2ユニット グループディレクターの眞鍋敬氏が登壇。
眞鍋氏は「ワークスタイル変革は以前から話題になっていた。テレワークがその代表だが、コグニティブを使うと別のやり方があるのではと言われ始めている」と、切り出した。「最近、顧客の行動が変わり始めたという声を聞く。お客さまが店舗に来ない。ほとんどECで済ませてしまう。また、海外で競争する必要が出てきた。これらに加えて、労働人口が減少する中で、仕事の量は減らない。仕事に対する価値観も変わってきており、1週間に3日働けばよいと考え方にどういう施策を講じるべきか。日本企業の課題は山積みだ」と問題提起する。
眞鍋氏は日本企業の実態に即して語る。「ワークフローを変更し、使いやすいもの、意思決定を早めるものにする。あるいは執務環境を改善する。場所、時間の自由度を増すと、労働参加者が拡大する。1日、2時間だけ子どもの世話をしながら自宅で働いてくださいということもできるようになる。その際に、人事制度や評価の見直しが必要となる。制度を変えるには、リアルタイムの情報交換が必要で、バックオフィスの書類を全て電子化する必要がある」という。
「これらの課題に対する解決方法には共通性がある。ITが解決するもの、ITで解決できないものがある。例えば、評価制度の見直しはITが解決できない。総務・人事などの部門を巻き込んで、雇用形態、就業制度、評価制度などを変えなければならず、法制度や社内規定に縛られるので、企業トップ、人事・総務などの部門の関与が必ず必要となる」とした。
一方、「狭義のワークスタイル変化ではワークフローを変えたり、デバイスを良いものにしたり、時間の自由を増やしたりするなど、システムやICTでできることだ」と述べた。
次に眞鍋氏はモバイルワークについてのIDCの見解を紹介した。
「IDCはモバイルワークについてオフィス系、非オフィス系、在宅型などの定義を持っていて、それぞれが世界的にどの程度の比率にあるか調べている。モバイルプロフェッショナルはテレワークに該当するが実施している企業は10%程度と少ない。実施していない企業は60%。中小企業では大企業に比べ特に実施率が低い。このギャップを解消していくことが日本の生産性向上のポイントとなる」を要点を指摘した。
また、「テレワークを実施している企業は今後、さらに利用を拡大していこうという傾向にあるのに対して、テレワークを行っていない80%の企業は今後も実施の計画はないとする企業が多い。これは、セキュリティやコストが主なネックとなっている。しかし、テレワークを実施している企業と実施していない企業では今後、競争力に大きな開きが出てくる」と結論付けた。
続いて眞鍋氏は「デジタルトランスフォーメーション」について解説した。
「これからのICTの世界をけん引していくテクノロジーは、クラウド、モバイル、ソーシャル、ビッグデータの4つ。ただ、これだけでは実際のビジネスは回っていかず、イノベーションアクセラレーターを考える必要がある。次世代セキュリティ技術、AR(拡張現実)、IoT、認知システム、ロボティクス、3Dプリンタなどを産業分野にどのように生かして行くべきかを考えるのが、デジタルトランスフォーメーションだ。
IDCはデジタルトランスフォーメーションについて、企業が第3のプラットフォームを使って、新しい製品・サービス、新しいビジネスモデル、新しい関係を創り、新しい価値を提供し、競争力を強化することと定義している」(真鍋氏)
その実例として眞鍋氏は配車サービスUberを挙げた。「ビジネスモデル全体を変化させた。デジタル化とは異なるデジタルトランスフォーメーションだ。バックオフィスをデジタル化し、コストを20%削減させるのはデジタイゼーション。もっと劇的にコストを10分の1にするのがデジタルトランスフォーメーションだ。時間と場所は従来、われわれが仕事を進める上でのネックだったが、これが第3のプラットフォーム、あるいはイノベーションアクセラレーターにより、変えることができるようになった。ポイントは時間と場所の制約をどう取り払うかだ」。
この中でコグニティブシステム、認知システムは非常に重要な役割を果たすことが分かってきたという。「コグニティブシステムの市場規模は年間、倍々ゲームで伸びている。人間の意思決定を、バイアスが掛かっていないエビデンスを基に補助するシステムがコグニティブシステム。一般のAIとの違いはわれわれの意思決定を補助してくれるもの。ここが重要だ。AIの普及で人間の仕事がなくなるのではと言われているが、この議論は20年前に1度あった。オフィスにPC、ワープロが入り、仕事が減ったかというと、かえって増えた。人間の適応力は優れている」(眞鍋氏)
コグニティブシステムをどう使うのか。眞鍋氏は「日本では、銀行・保険の分野では既に使われているが、業種をまたがって使えることが重要だ。2019年には流通、製造などの領域で日本でも大いに使われ、コグニティブの利用は当たり前になっていくだろう」と展望する。
コグニティブの具体的な利用方法だが、「どのようにデータを集め、どう分析し、どのように顧客に伝えるか。このうち、どうユーザーに伝えるかが重要だ。アプリケーションの一部に組み込まれることが大切で、今後のワークスタイル変革のポイントだ」とした。
最後に眞鍋氏は「ワークスタイル変革は必須であり、競争力を得るための独自の変革が必要だ。市場の動きはわれわれの想像以上に早く、ダークデータが脚光を浴びる可能性がある。まずはバックオフィスの変革、紙の資料をデジタル化し、顧客とどのような関係を再構築できるか探索することだ。ワークスタイルの変革においてIT部門の役割は重い」と結んだ。
コグニティブがワークスタイルをどう変革するのか
続いてのIBM講演「テクノロジーとコラボレーションの進化が可能にする『より自分らしい働き方』」では、日本アイ・ビー・エム ソーシャル事業部 技術理事の行木陽子氏が登壇。行木氏は、コラボレーション・ツールについてのIBMの基本的な考え方について「柔軟に働く場所を提供する。時間、場所の制約から解放されて働くことを可能にする。これまで共有されていなかった情報を活用して働く。世界各地のつながっていなかった人々と協同でイノベーションを起こしていく、そうした素地を提供していく」と解説する。
次いで行木氏は働きながら大学院で博士号を取得したある女性社員の例を引き、Verseをどのように活用し、ワークライフバランスを自分でデザインしていったかを紹介。IBMのコラボレーション関連の製品開発の基本姿勢として【1】働くことにフォーカスする【2】ユーザーインタフェースへの注力【3】コグニティブ――の3つを挙げた。
行木氏は、その具体化として、新製品として予定されているToscanaについて解説。Toscanaは小規模チームでタスクを動かす場合の新しいツールとして期待されている。クラウドの環境を自分で作り、過去のデータもすぐ活用でき、すぐにチームができる。ファイルの共有もクラウド上ですぐにできる。情報交流も瞬時に行える――などの特徴について行木氏はデモを交えて紹介した。
コグニティブについては、コラボレーション領域で活用するために2つの要因に配慮した点を指摘した。1つは、パーソナルアシスタント、もう1つは、ビッグデータを活用した最適なアドバイスを行うことだ。行木氏は、ビデオによるデモで解説しながら、Watsonが推奨してくれた行動が蓄積されていく様子を紹介。また、文章を読む前に、文章の中身を分析してくれるトーンアナライザー機能、文字を入力中にクラウド内の関連ファイルを指摘してくれる機能など今後、登場してくる製品機能について説明した。
続いて同社 ソーシャル事業部 第一テクニカルセールス部長の松浦光氏は小規模組織におけるコグニティブシステムの活用、既存のアプリケーションに蓄積されているデータをコグニティブシステムでどのように活用していくかについて解説した。
Notesは登場以来既に20数年間使われているが、これまでビジネス活用にしていたSoR(System of Record)・構造化データではなく、ダークデータをWatsonに理解させ、学習させ、推論させて、どう活用していくか。松浦氏はWatsonを利用した、2つのデモを行った。
1つはNotesに保存されている文章を新規文書として保存する際に、自動で文章のカテゴリーを付加するデモ。Watsonは文書中のキーとなる用語に着目し、700文書にアクセスし、95%という確率で、「この文書はxxについての文書だ」と判断した。
もう1つのデモは、人間が喋った言葉をWatsonがどのようなジャンルに関わる話なのかを判断するデモ。これによって「WatsonをPCで活用するために新たにUIを作成する必要がない。開発する必要があるのはボット側のAPIのアプリケーション開発だけ」という。
この2つのデモで実現された機能を組み合わせると、さまざまな問い合わせが可能となる。最後に、松浦氏コグニティブを使うと、「これまで人間だけでは見えていなかったことが見えてきて、皆さまや、皆さまのお客さまの働き方が大きく変わるのではないか」と結んだ。
関連記事
 IBM、「コグニティブ時代の開発者」を支援する4つの新施策を発表
IBM、「コグニティブ時代の開発者」を支援する4つの新施策を発表
米IBMは、インドのバンガロールで開催されたイベントにおいて、クラウド、コグニティブ、IoTなどの新技術に携わる開発者を支援するための4つの新施策を発表した。 コグニティブ技術も生きる、IoTの最新12社事例――製造業、自動車、ヘルスケア・医療、顧客対応、農業、建築・公共
コグニティブ技術も生きる、IoTの最新12社事例――製造業、自動車、ヘルスケア・医療、顧客対応、農業、建築・公共
社会一般から大きな注目を集めているIoT(Internet of Things)。だが、その具体像はまだ浸透しているとはいえない。今回は、2016年5月25、26日に開催された「IBM Watson Summit 2016」の幾つかのセッションの模様から、その最新事例をお伝えしよう。 IBMがWatsonを「AI」と呼ばない本当の理由
IBMがWatsonを「AI」と呼ばない本当の理由
「コグニティブコンピューティング」と呼ぶAI(人工知能)領域のテクノロジーに注力するIBM。だが、同社はAIという表現を使っていない。その背景を探る。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
編集部からのお知らせ

 日本アイ・ビー・エム ソーシャル事業部理事 事業部長 田崎慎氏
日本アイ・ビー・エム ソーシャル事業部理事 事業部長 田崎慎氏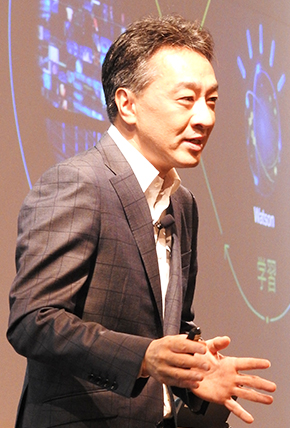 日本アイ・ビー・エム 常務執行役員 コグニティブ・ソリューション事業担当 松永達也氏
日本アイ・ビー・エム 常務執行役員 コグニティブ・ソリューション事業担当 松永達也氏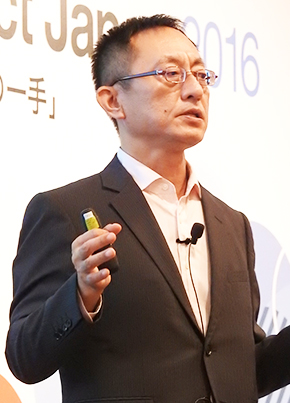 IDC Japan リサーチ第2ユニット グループディレクター 眞鍋敬氏
IDC Japan リサーチ第2ユニット グループディレクター 眞鍋敬氏 日本アイ・ビー・エム ソーシャル事業部 技術理事 行木陽子氏
日本アイ・ビー・エム ソーシャル事業部 技術理事 行木陽子氏 日本アイ・ビー・エム ソーシャル事業部 第一テクニカルセールス部長 松浦光氏
日本アイ・ビー・エム ソーシャル事業部 第一テクニカルセールス部長 松浦光氏



