第1回 デスクトップの仮想化とVDIの違いを知っていますか?:Windows Server 2008 R2によるVDI実践入門(3/4 ページ)
RDP(Remote Desktop Protocol)/RDS(Remote Desktop Services) ― リモートからのデスクトップ利用
前のページで説明したMED-VやApp-Vは集中管理型とはいっても、クライアントPCに仮想マシンや仮想アプリケーションを配備する必要がある。これはオフラインすなわち外に持ち出す必要があるPCでも利用可能というメリットをもたらす。しかし一方で、データも処理も各クライアントに依存するため、その分のクライアントPCの管理コストは残ってしまう。
そこでデータも処理もサーバ・ルーム(に置いたサーバ上)で行いたいということならば、MED-VやApp-Vとは異なるテクノロジを選択し、リモートでの利用を考えなければならない。その1つが以下で説明するリモート・デスクトップの技術である。
マイクロソフトは、リモート・デスクトップを中心とした、リモートからコンピュータを利用する技術も仮想化の一種として扱っている。プレゼンテーション・レイヤ(簡単にいえば画面やキーボード、マウスなどのUI)を仮想化して、あたかも自分の目の前にマシンがあるように見せる技術だから、プレゼンテーションの仮想化というわけだ。
例えばシンクライアントから別のマシンを操作する場合、マイクロソフトの技術としてはRemote Desktop Protocol(RDP)*1を利用することになる。
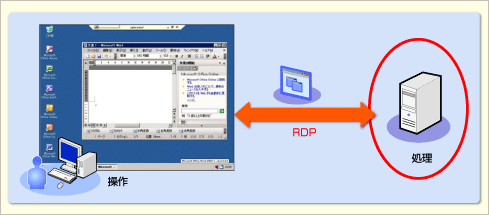 Remote Desktop Protocol(RDP)によるプレゼンテーションの仮想化
Remote Desktop Protocol(RDP)によるプレゼンテーションの仮想化プレゼンテーションすなわち画面を含むUIを仮想化することで、操作と処理を分離して別々のPCで実行できる(2台のPC間の通信はRDPで行う)。これにより、操作側すなわちクライアントPCへの依存度は、分離された処理の分だけ下がる。
*1 RDPを使う際、リモート・デスクトップ接続(Remote Desktop Connection=RDC)を利用することになる。今回はあえて分けずに、どちらもRDPとして解説する。
このRDPは、上図のように操作用PCと処理用PCを1対1でつなぐだけでなく、1対多すなわちサーバ集約型のサービスとしても利用できる。以前はターミナル・サービスと呼ばれていたが、Windows Server 2008 R2からはリモート・デスクトップ・サービス(RDS)と名前を変えて提供されている。
「エンドユーザーは必要なアプリケーションを利用できればよい」と考えれば、おのおののPC上でアプリケーションが動く必要はない。サーバにインストールされたアプリケーションをリモートから利用できればそれでよいとも考えられるわけだ。常にネットワークでつながっていることが前提とはいえ、アプリケーションの管理はサーバに集約され、データも処理もサーバで行われるため、セキュリティやコンプライアンスの面でも有効な手段として利用されている。
ただ、Windows Server 2003 R2まではサーバのデスクトップをクライアントPCに表示し、その中でアプリケーションを使わなければならないという制限があった。しかしWindows Server 2008からは、サーバ上にインストールされた各アプリケーションを直接起動してウィンドウ表示する仕組み(RemoteApp)が用意され、利便性は一気に向上した。
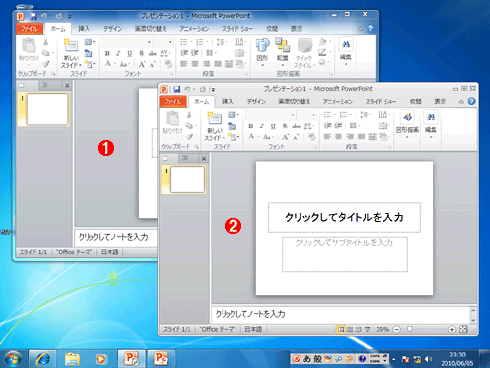 RemoteAppによるアプリケーション利用の例
RemoteAppによるアプリケーション利用の例ローカル・マシンのWindows 7上で動作するPowerPoint 2010(左奥。(1))と、サーバのRemoteApp上で動作し、Windows 7に画面が転送されているPowerPoint 2010(右手前。(2))の画面を並べてみた。見た目はほとんど同じだが、RemoteAppの方はファイル保存時にサーバのディスクが表示されるところで、エンドユーザーがリモートであることを意識するだろう。
(1)ローカル・マシンにインストールされたPowerPoint 2010。
(2)サーバにインストールされたPowerPoint 2010をRemoteAppで表示している。一見しただけでは(1)と区別がつかない。
実は、RDSやRemoteAppには弱点がある。それは、アプリケーションがサーバOS上で直接動作するという点だ。つまりWindows Server 2008 R2のRDSで業務アプリケーションを提供しようとすれば、そのアプリケーションは Windows Server 2008 R2に対応していなければならない。
新しいOSで従来のアプリケーションのすべてが正常に実行できるとはいい難く、しかも64bit版しか提供されていないWindows Server 2008 R2ではさらに敷居が高くなる可能性もある。
次のページでは、これまで紹介してきた仮想化技術を踏まえながら、VDI(Virtual Desktop Infrastructure)の概念や動作原理、Windows Server 2008 R2におけるVDI機能について説明する。
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
編集部からのお知らせ





