「製造のデジタル化」に挑むマネジャーが知った「従来型組織のDX推進」の秘策とは:DXを成功させるための組織論(2)
製造業においてもDXの推進は重要な施策だ。しかし、実際には製造業ならではの壁にぶつかることも少なくない。本田技研工業で「製造のデジタル化」に挑むマネジャーが取った解決方法とは何だったのか。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
「戦略はあるのか?」「当初の計画通りにやっているか?」
現場でこういった声を聞くことがありますが、こうしたマネジメントがいつも正しいわけではないと考えています。著者は自動車製造において70年以上の歴史を持つ本田技研工業で「製造のデジタル化をどう進めるべきか」という課題に向き合っていますが、なかなか思うように進まず苦労をしています。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は企業の命題となりつつあります。ITサービス系の企業は当然として、製造業の分野においても「業務のデジタル化」は検討すべき重要な課題です。本稿は、これまで著者が取り組んできた「従来型組織のDX推進」において発生する問題やその対処、未来に向けた取り組みについてマネジメントの観点で紹介します。ポイントは以下の3点です。
- 正攻法で攻めるのではなく、小さなアジャイルチームで実績を残す
- 「現場から見て本当に必要なサービスだけ」を開発する仕組みを作る
- 周りからの指摘には「プロダクト」で対処する
従来型組織で障壁になる「必要性が少ない作業」
自動車メーカーは典型的な製造業の体系を持っています。経営者から本部長、本部長から部長というように順次ブレークダウンさせた各レベルの方針を基に、実務者は達成手法、達成目標を検討します。それらをまとめた資料を作成し、上長から承認を得る、といった体系です。
こういった組織でDXを考えるとどうなるか。
まず、関連する各部門が自らの戦略の重要性を認めてもらうための資料作成が始まります。参加する部門も多岐にわたり、本田技研工業であれば戦略部門、技術部門、工場部門、IT部門などが参加します。IT部門や技術部門など技術に関する部署は、部門間を横断するような提案になります。そのため、各部門と戦略のバランスを調整する必要があり、「あちらを立てればこちらが立たず」と悩むこともあります。しかも各部門だけではなく、ITベンダーやコンサルタントも参加すると、作られる資料の数は膨大になり、検討する時間も資料の数だけ増えます。
「自部門がどうあるべきか」を決めることは重要ですので、そのために多くの時間を割くことは正しいでしょう。ただ「資料として、いかにきれいにまとめるか」を追求することに多くの時間が割かれている印象があります。きれいな資料は見栄えが良く、承認も得やすいかもしれません。ですが、難易度が高く、困難を極めると思われる施策がまるで「簡単にやり切れる」ように表現できてしまうため、著者が作成する場合は注意するようにしています。
失敗から理解した「正攻法では駄目」な理由
DXを進めるためにはこうした文化を変えていく必要があります。とはいえ「そのために何をすればいいか」は明確に分からないことが当たり前です。われわれの部門でも幾つかの手を打ちました。
例えば、データを収集、分析し、業務の流れを見える化するプロジェクトを立ち上げたことがありました。しかし、このプロジェクトは失敗に終わりました。コンサルタントとも協力し、かなり費用をかけ、現場のデータを可視化する仕組みを幾つか構築したものの、既に長年の経験から確立された指標を持っている現場には定着しなかったのです。現場の温度感に合わせられなかった著者の責任だと考えています(参考記事:「俺たちが必死で稼いだ1円、1秒をITに使わせない」とまで言われた ホンダの挑戦)。
この失敗を踏まえ、著者は「抜本的に仕組みを作り直し、一気にデジタル化を進める」という正攻法では駄目だと理解しました。そこで次に目を付けたのが「アジャイル開発」でした。若手のエンジニア(本田技研工業 船戸康弘氏)が内製開発に向けて検討していたこと。そして、柔軟な開発方式であるXP(エクストリームプログラミング)の経験を著者が持っていたため、抵抗感が少なかったこともアジャイル開発を選んだ理由です。アジャイル型開発で現場の業務を分析し、現場が本当に必要とするサービスを素早く提供し、「ITは時間も金もかかる」という意識を変えることでDXを進めようと考えました。
結果的にこの「小さな価値創出から始める」アプローチは現在軌道に乗り、徐々に規模を拡大しています。
「ITは時間も金もかかる」という意識を変える
アジャイル開発のチーム構築において最も重要だと著者が考えるのは「マネジャーとして覚悟を決め、若手を全力で肯定すること」です。新しい仕組みは簡単には受け入れられません。著者の場合は一からサービスを作り始めることやOSS(オープンソースソフトウェア)を活用する上での懸念の責任を負うこと、何より「関係部門全ての承諾」がない状態でのスタートに戸惑いがありました。しかし、マネジャーがその状態ではチームは能力を存分に発揮できません。そのため、覚悟が重要なのです。
覚悟の一端として、チーム内での資料作成を原則禁止としました。資料が必要なのは、それがなければ提案内容や進捗(しんちょく)が分からないからです。ですが、一緒に実物(プロダクト)を見ながら解決方法を探ることで資料がなくとも価値ある提案や進捗の確認ができるようになります。
開発を始めようとしても使える人材や予算が限られているケースも多いでしょう。本田技研工業の取り組みでは、開発するサービスは「現場から見て本当に必要なサービス」だけとしました。その代わり、現場への費用負担が軽い小さなシステムを毎週提供するという仕組みです。開発者と現場のユーザーは一緒にスクラムチームを組み、価値が出るまで機能を変えることとしました。
このおかげで、これまでは予算申請や修正にかかる費用といったさまざまな都合で現場が諦めていたサービスを提供できるようになりました。「すぐに作ってくれるし、改修もしてくれる。負担も軽くて、すごくいい」と現場の支持を得ることができました。
周りからの意見には「プロダクト」で対処する
こうした取り組みをしていると、周りからさまざまな意見が上がってきます。「一部門が独自に進めるとシステムがバラバラになる」「市販の統合パッケージの方がいいのでは?」「戦略と違うのでは」などなど……。こうした意見にどう対処すべきでしょうか。
著者は、まずありがたく受け止め、その上で前述したプロダクトありきのサービス開発「プロダクトファースト」で進めることが重要だと考えています。本田技研工業のように現場とともに作り上げるサービスを毎週提供していると現場からの信頼は厚くなります。なにせ現場は実際に「動くもの」を見ているからです。
さまざまな意見や指摘は大半が「組織の壁や従来的な概念が生み出すもの」と著者は考えます。そういったものは「リアルな現場の声」に弱いものです。意見に対して説明はしっかりすべきですので、著者が取りまとめをすることもあります。ただ、こうした「現場の後ろ盾」があるので説明も必要最低限で済むのです。
もちろん、ベンダーロックインに気を付け、インフラを統一して業界標準に合わせた柔軟性の高い環境で構築するなど技術的な懸念を減らしていることも「説明が簡単でよい理由」の一つです。
若手世代を受け入れ、上の世代とのハブになる
著者がマネジメントをするようになって感じたのは、「上位者との関係やセクショナリズムから、観点が顧客から離れがちになる」ということです。若手に自分と同じ経験(克服感、達成感など)を感じてもらおうと過去のことばかり話してしまいそうになります。ですが、昔と今では価値観が大きく変わっています。
著者は若手世代を「徹底した合理主義で目的志向。優秀で優しくとても面白い。そして『最短距離』が好きな部分もある」と分析しています。過去の経験の話をするだけでなく、これまでの「当たり前」を疑い、「これおかしくないですか? 自分ならこうしますよ」といった若者の意見を取り入れ、育てていくという姿勢が40〜50代のマネジメント層に必要なのではないでしょうか。
筆者紹介
松本 芳宏(まつもと よしひろ)
DXの流れに乗り、生産技術企画部門のデジタル領域 課長として生産部門のデジタル対応を担う。同社内でいち早くアジャイル開発を取り入れ、現在は取り組みに賛同するユーザー(ファンユーザー)増加と領域拡大に向けて奮闘中。
特集:DXを成功させるための組織論〜エンタープライズ企業に学ぶ DXを進めるための組織作り〜
アジャイル開発手法やコンテナを利用したマイクロサービス化など「業務のデジタル化」のベストプラクティスは整いつつある。しかし、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が順調に進んでいるようにはみえない。これは、企業の中で「DXはサービス開発の新しい手法」としか捉えられていないためだ。DXの神髄とは「企業のビジネスがデジタル化すること」で、そのためにはDXに適した組織が必要だ。本特集では従来型の組織構造を持つイメージが強いエンタープライズ企業の事例を中心に「DXを実現するための組織を作るためには何が必要か」について紹介する。
関連記事
 日本企業にも「オープンソースプログラムオフィス」が必要、「企業のためのオープンソースガイド」が公開
日本企業にも「オープンソースプログラムオフィス」が必要、「企業のためのオープンソースガイド」が公開
Linux Foundationの日本支部、Linux Foundation Japanが、「企業のためのオープンソースガイド」をWebで公開した。日本でも、テクノロジー企業、一般企業を問わず、OSSの利用を組織として管理し、戦略的に考える必要性が生まれているという。 「俺たちが必死で稼いだ1円、1秒をITに使わせない」とまで言われた ホンダの挑戦
「俺たちが必死で稼いだ1円、1秒をITに使わせない」とまで言われた ホンダの挑戦
固いイメージのある製造業でありながら、アジャイル開発の導入に成功した本田技研工業。自由な風土があるから導入できたのだろうとうらやましがられることも多いそうだが、実はさまざまな失敗と摩擦を乗り越えて今があるという。 DXのリーダー組織は専任組織の「第2のIT部門」 DX人材の確保は共創が鍵――IDC調査
DXのリーダー組織は専任組織の「第2のIT部門」 DX人材の確保は共創が鍵――IDC調査
国内企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)で中核を担う組織は、デジタル変革のために設置された専任組織の「第2のIT部門」が最多であることが判明。また、DXの実行局面で課題となる人材については、企業の枠を超えた人材確保や共創型デジタルプロジェクトが鍵になるという。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

 若手が中心となって進める開発の風景
若手が中心となって進める開発の風景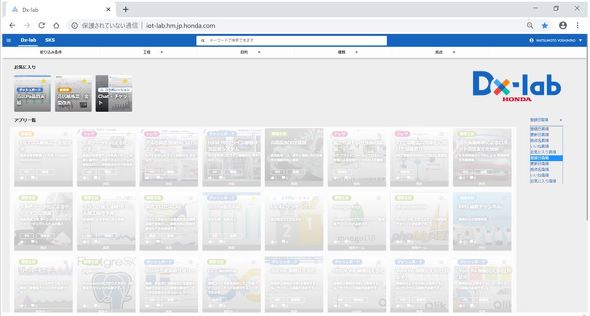 プロダクトと関連資料は「DX-Lab」というポータルサイトにアップロードし、社内共有している
プロダクトと関連資料は「DX-Lab」というポータルサイトにアップロードし、社内共有している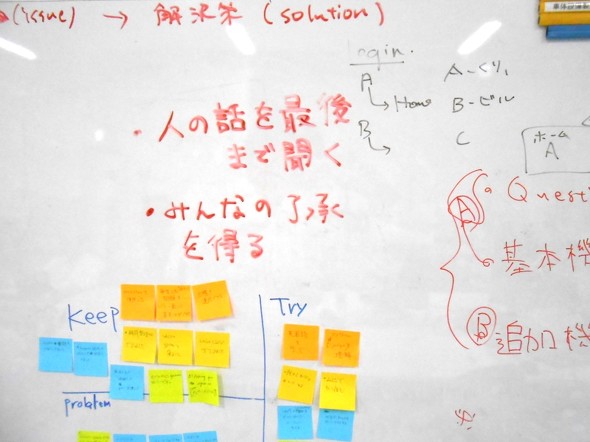 ホワイトボードには「人の話を最後まで聞く」と書いてある
ホワイトボードには「人の話を最後まで聞く」と書いてある



