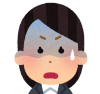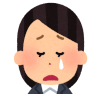「どうして○○したの?」で誤解を与えていませんか? エンジニア育成の土台となる関係性作りで必要なこととは:エンジニア育成担当者のためのはじめの一歩(2)
自分の技術力に自信がなく、新人や後輩の育成方法に悩むエンジニア育成担当者に向けて、すぐに使える育成スキルを紹介する本連載。第2回は、コミュニケーションのすれ違いを防ぐための土台となる関係づくりに必要なことについて。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
前回の記事では、技術力だけでなく他者を受け入れることが育成に重要だとお伝えしました。第2回では、育成場面でよく使いたくなる「どうして?」といった問いかけをするときに発生する問題と、その要因を紹介します。そして、コミュニケーションのすれ違いを防ぐための土台となる関係づくりについて、避けた方がよいことと、効果的な方法の中から簡単に実践できることを紹介します。
「どうして?」と問うことで起きるすれ違い
新人育成のときに、問いの定番となる「どうして?」「何で(なんで)?」は、よく使っている方もいますよね。しかし、「どうして?」「何で(なんで)?」を投げ掛けたときに、想定した答えや行動が返ってこない経験をしたことはありませんか?
(あれ、あまり見ない方法を使っているから理由があるのかな。確認してみよう)
どうして、この方法を試したの?
こちらの例では、先輩が見慣れない方法を使っているから理由を話してもらおうと「何で(なんで)、この方法を試したの?」と聞いたのですが、先輩の想定とは違い、後輩が先輩に謝罪してしまいました。同じように理由を聞かれたときに、後輩が黙り込んでしまうケースもあるでしょう。先輩は悪気なく疑問に思ったことを聞いているわけですが、後輩は責められているように感じてしまったようです。
悪意なく使った言葉が、後輩を苦しめてしまうのはどうして?
先輩には責めるつもりがなかったのにもかかわらず、後輩は責められているように感じてしまったのは、どうしてでしょうか?
言葉は、必ずしも文字通り受け取られるわけではなく、同じ言葉を発したとしても、発言の状況、会話している人の関係性によって受け取り方が異なることが分かっています。そのため、先輩は後輩が何を考慮しているか知るために聞いたとしても、関係性が良好でなければ誤解につながります。
分かりやすいように少し極端な例にしていますが、一度自分が後輩の立場で考えてみると、どうでしょうか?
ある先輩は、いつも私が意見を出したときには、否定的に反応します。さらに、ことあるごとに「こうすべきだ」と意見を押し付けてくるのです。そんな先輩から「進捗(しんちょく)、どう?」と聞かれたら、どう感じるでしょうか?
もう一人の先輩は、いつも私に意見を聞いてくれたり、「困ったことはない?」と声を掛けてくれたりしてくれます。さらに、私が任されている仕事が終わらないときには助けてくれることもあります。そんな先輩から「進捗、どう?」と聞かれたら、どう感じるでしょうか?
先輩に対する印象や関係性によって、同じ発言を聞いても異なる印象になることがイメージできたかと思います。前者の否定的な先輩に言われると、責められているように感じやすく、後者の気に掛けてくれる先輩からの発言であれば、フォローやアドバイスのために言ってくれていると感じますよね。
ここまで説明してきたように、両者の関係性や、後輩が抱く先輩への印象によって、同じ言葉を発したとしても後輩の受け取り方に影響を与えます。そのため、先輩からは理解を確認するために悪気なく聞いた「どうして?」に対して、後輩が責められていると感じるか、理解を確認されていると感じるかが変わります。「どうして?」といった問いかけは、育成する上で頻繁に使いたい質問なのですが、誤解されやすい問いかけでもあります。
このことから、育成の場面では、円滑なコミュニケーションをするためにも、すれ違いによる誤解をなくすためにも、関係づくりが必要です。
【コラム】発言の状況によって受け取る印象が変わる
同じ言葉でも、発言の状況と関係性によって受け取り方が異なると説明しましたが、前者の状況についてもう少しだけ紹介します。
例えば、「将来アメリカで仕事をしたい」と先輩に話したときに「英語を勉強するのはどう?」と言われると、自分のために話をしてくれていると感じやすいですよね。それに比べ、英語のドキュメントの理解が足りず先輩に迷惑を掛けてしまった後に「英語を勉強するのはどう?」と言われたら、先ほどよりも皮肉を言われている感じがしませんか?
このように、発言する状況やタイミングによって、同じ発言でも受け取り方が変わってくるのです。
関係づくりをするときに避けること
では、どうすれば関係づくりができるのでしょうか? ここからは、関係づくりをするときに避けてほしい行動と、効果的な方法をお伝えします。
関係づくりをするときに避けてほしい行動は、「人前で相手のことを否定する」「話したことを勝手に漏らす」「疲れているとき、後輩に対応する」「機嫌が悪いとき、後輩に対応する」です。それぞれ紹介していきます。
人前で相手のことを否定する
人前でなくとも、相手のことを否定することは控えたいところですが、人前で否定することは特に気を付けてください。周りの人から後輩への評価が下がってしまいますし、後輩も自分の評価を下げられていると感じるでしょう。また、後輩がいない場で、後輩のことを否定するような発言も控えましょう。
話したことを勝手に漏らす
この先輩になら話していいと思って話していることは、他の人に伝わることを想定していないので漏れるとショックです。さらに、次から人に言えない話を相談できなくなってしまいます。
メンターとして、上司に伝えた方がいいと思う場合は、事前に後輩に確認し、共有することを許可してもらえるようにお願いしてみましょう。それでもNGと言われたら諦めましょう。もしも、不慮の事故で他の人に伝わってしまった場合は、正直に話して謝罪し、二度としないことを約束しましょう。
疲れているとき、後輩に対応する
疲れているときに後輩に対応すると、後輩に対して必要以上に厳しく接したり雑に接したりしてしまいます。人が1日に我慢や思考できる量には限界があるので、疲れていたり、締め切りに追われて焦っていたりすると、相手への接し方に気を配ることが難しくなります。そんなときは、後から悔やむような良くない接し方をしてしまいがちです。終業に近い時間よりも、始業に近い時間を確保したり、休憩をとった後に接したりするとよいでしょう。
機嫌が悪いとき、後輩に対応する
機嫌が悪いときに後輩に対応すると、相手に対してネガティブな感情を持ちやすくなります。人の仕組みとして、機嫌が悪いから相手の言葉を悪く受け取ったのか、相手が嫌なことを言ったから機嫌が悪くなったのかを区別することが難しいのです。そのため、機嫌が悪いときに後輩に接すると、接し方や発言のせいで機嫌が悪くなったと誤認識しやすくなります。自分の機嫌が悪いと認識しているときは、できるだけ後輩に接するのを控えましょう。
関係づくりをするときに効果的な方法
関係づくりをする初期段階につかう簡単で効果的な方法は「接する頻度を増やす」「似ているところを探す」「自分の情報を共有する」です。
接する頻度を増やす
人は触れる回数の多いものに好感を抱きやすくなります(単純接触効果)。しかし、これは既に苦手意識を持っている場合には逆効果になりますので、お気を付けください。
接する頻度を増やすとはいっても、何度も話すきっかけを作るのも労力を使います。そのため、5分程度、毎日定期的に話をする時間を確保しスケジュールに入れてしまうのがお勧めです。
さらに良いことに、後輩が「わざわざ相談することでもないかな」と思っていることも、話す機会があることで「そういえば〜」などと情報をキャッチアップすることにもつながります。「困ったら相談してね」と伝えることに比べて格段に情報を得られます。オフィスで働いている場合であれば、声を掛けて立ち話が気楽ですね。
リモートの場合は、カメラをONにして話す方がいいですが、抵抗がある人もいるのでやんわり確認してみるのがお勧めです。また、チャットツールだと、プライベートな雑談も書き込めるような部屋を作っておくと接触機会を一気に増やせます。先輩が進んで雰囲気作りをすることで効果を高められます。
似ているところを探す
人は似ていることを見つけることで好感につながります(類似性)。似ていると良いものはたくさんあって、年代や、出身地、大学、学部のような属性情報や「よく遅刻する」のような行動特性、「ユーザーが使いやすいものを作りたい」のような価値観、休みの過ごし方、食べ物や音楽の好みといった趣味嗜好(しこう)などが挙げられます。
この趣味嗜好を知る手軽な方法として、自分の好きなものを紹介する「偏愛マップ」というツールがあります。画像検索するとたくさん出てきますので、参考にして書いてみてください。
似ているところを探すのが目的なので、昔はまっていたけれど今はあまりやっていないことも載せておくと会話が広がりやすくなります。書く項目の例としては、マンガ、アニメ、音楽、映画、本、食べ物、趣味、テレビ番組、有名人、お店、場所、リラックス法、好きな休日の過ごし方、など。他の人と共通点が見つかるように幅広く書いてみましょう。
この偏愛マップを見ながら一緒に話をすると効率的です。より効果を高めるためには、好きなものを説明するのではなく、他の人が興味を持てそうなもの、共通点になりそうなものについて質問し合うのがお勧めです。私の偏愛マップを見せたところ、「私も雀魂にはまっています」「論理学についてまた今度情報交換したいです」と言われました。話すきっかけが増えることで、「接する頻度を増やす」ことにもつながりますね。
偏愛マップの作成から対話までを短時間で実施するなら、セットにして時間を確保してしまうのが準備もいらず気楽です。メンターとメンティーの関係を深めるために2人でやる場合は、30分確保し、10分で偏愛マップを作り、10分ずつ質問タイムにして話してみるのがいいでしょう。開発チームの6人で関係づくりをするなら、1時間確保し、10分で偏愛マップを作り、8分ずつ交代に質問タイムとして話をしてみるのもよいでしょう。偏愛マップは、一度作ると使い回せていろいろな人と共通点が見つかります。時間をかけて作り、社内のWikiなどに公開するのも有効です。
自分の情報を共有する
自分の情報を共有すると相手のことを理解でき、関係性づくりに役立ちます。人は相手が情報を開示すると信頼してくれていると感じ、自分の情報を開示しやすくなります。そうすることで、後輩のことを理解する先輩に近づけるのです。自分のことを理解してくれている先輩がいると、安心できますよね。
先ほど紹介した、似ているところにつながりそうなプライベートな会話をするのも効果的です。より効果が高いのは、過去の失敗談を共有することです。このとき、失敗談を話しているようにみせかけた自慢話をしてしまうとマイナスな印象になってしまうのでお気を付けください。
参考文献
- 三宮 真智子,(2017),誤解の心理学
- 和田 実,増田 匡裕,柏尾 眞津子,(2016),対人関係の心理学 親密な関係の形成・発展・維持・崩壊
著者紹介
川鯉光起
情報工学を修了し、ソフトウェアエンジニアとスクラムマスターとして働いた後、現在は、アジャイルコーチ、リーダー研修、ITエンジニア育成コンサルタント、コーチングを仕事にしています。アカデミックな情報を職場で応用することが得意で、教育心理学を始めとして、認知科学、社会心理学、臨床心理学など、「科学の力を借りて楽しく働く支援」することを生きがいに働いています。
著書に、「理論と事例でわかる自己肯定感」「理論と実践でわかる職場の教育」などがあります。
著書:https://education.booth.pm/
連絡先:learning.process.update at gmail.com
Twitter:https://twitter.com/kawagoik
関連記事
 「IT業界あるある物語」で覚える、新人エンジニア/メンター/リーダーが知らないと現場で生き残れない18の常識
「IT業界あるある物語」で覚える、新人エンジニア/メンター/リーダーが知らないと現場で生き残れない18の常識
人気過去連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する@IT eBookシリーズ。第39弾は「新人が知らないと現場で生き残れない18の常識」だ。新人エンジニア、そして新人の先輩になる若手エンジニアたちに、参考にしてほしい。 「コーチングはウザい」と思われちゃった僕のしくじり体験
「コーチングはウザい」と思われちゃった僕のしくじり体験
「コーチングをかじった人ってすぐに質問攻めにするよね」「威圧的だよな」「キラキラした理想ばかり語ってウザい」――困っている人を支援したいと思って勉強したのに、もし、周りから煙たがられていたら……そうならないために気を付けたいコーチングとの関わり方とは? 課題は作業環境の整備、アスクルがテレワークの実態調査
課題は作業環境の整備、アスクルがテレワークの実態調査
アスクルは「テレワークの活用における実施率や導入に伴う課題」に関する調査の結果を発表した。2021年4月時点のテレワーク制度の導入率は34.3%だった。テレワークの課題として「社内コミュニケーションの取りづらさ」を挙げる人が増えているという。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.