第275回 Aruduioへのマイコン供給でルネサスは変わるのか?:頭脳放談
ルネサスエレクトロニクスのArmコアマイコンがボードコンピュータ「Arduino」に採用されるという。これまでB2B分野を中心に展開してきたルネサスが、コンシューマー分野に手を広げる形だ。その背景には何があるのか、筆者が推察してみた。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
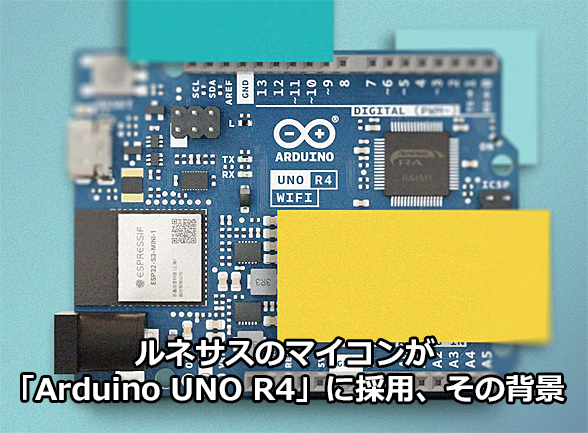 Arduino.ccのボードコンピュータ「Arduino UNO R4」
Arduino.ccのボードコンピュータ「Arduino UNO R4」「Arduino UNO R4」にルネサスエレクトロニクスのArmコアマイコンが採用されたという。これまであまりコンシューマー向けに力を入れて来なかったルネサスが、Arduinoにマイコンを供給する背景は? 筆者が推察してみる。
長らく続いた半導体不足だが、一服どころか一転、奈落の底をのぞき込んでいるような状況になりつつある。ご心配の方々も多かったのではないだろうか。
しかしマイコンに限ればいまだ不足の解消していない品種もあるほどだ。特に日本の場合、2022年来の円安のあおりもあり、外国製のマイコン関連製品については需給がタイトな上に値上がりも目立つ。
象徴的なのはワンボードコンピュータ「Raspberry Pi 4」の入手困難だろう。Raspberry Piシリーズは、かつてはマニア向けのボードコンピュータという位置付けで、秋葉原などにあるショップの通販で小口で販売されていた。
今でもマニア向けの人気は高い一方で、昨今は工業用途(組み込み用途)で大量に使われている。B2B市場に数百万台といった規模で流通しているための品薄らしい。Raspberry Piの40ピンの拡張端子は工業用途の「標準バス」的なデファクトになりつつあり、プロユースの拡張ボード類も多数登場している。コンシューマー分野で小口販売されていた製品がB2Bの世界で大成功しているのだ。
Raspberry Pi(マイコン機種のPicoは除く)は、Linux搭載のボードコンピュータであり、IoTネットワークの中ではエッジに位置付けられているような場所で使われることが多い。
その先、IoTネットワークの末端部分、センサーであったり制御であったりのノードで人気の高いコンシューマー向け製品に「Arduino」がある。秋葉原レベルでは知らない人はいないマイコンボードだが、B2B分野のマイコン関連の仕事をしている人の中には、触る気もない人がいるかもしれない。しかし今やArduinoの名のもとに巨大なエコシステムが出来上がっているのだ。
Arduinoって何?
マイコンボードの開発に大きな初期費用が必要であった、かつての状況とは様変わりなのである。今では無料のCADを使って誰でも安価に(数千円から)PCBを発注したり、マイコン製品を少量生産できたりするような世の中である。
クラウドファンディングでお金を集めてアイデアを物にするような流れもある。日本ではあまり盛りあがっていないのが残念だが、欧米でも中国でもそういった手法を駆使してベンチャーが立ち上がることが増えているように思われる。そんな世界の中でArduinoというイタリア起源のささやかな規模のマイコン開発ボードが巨大な存在感を示しているのだ。
なぜArduinoかと理由を問えば、そのオープンなエコシステムが挙げられるであろう。Arduinoの本家のArduino.ccがハードウェア/ソフトウェアを「設計」してはいるが、回路図もソフトウェアソースも全て公開されている。
商標に関しては制限があるようだが、Arduino互換と称するボードを製造しているメーカーも多数ある。大手のマイコンメーカー製の純正開発ボードでもArduino互換と称する拡張端子を備えているものが多い。STMicroelectronicsやNXPなど欧州半導体メーカーの多くが含まれる。そしてその端子に接続可能な周辺機器も多い。
また、ソフトウェアに関してもArduino互換と称するものの裾野は広い。「Arduino IDE」という名のIDE(統合開発環境)と、そこで使われているツールチェーンは大手ツールベンダーが提供する本格的なツールと比べたら機能的には限定されるものだ。
しかし各種ソースから提供されるライブラリなどを統合することで、非常に幅広いマイコンや周辺機器に対応できる一種の「ソフトウェア・バス」になっている。端的にいえばArduino環境で動作するソフトウェアであれば、ある会社のマイコン上で動かしていたソフトウェアを、全く別な会社のマイコン上に移植することが「秒」で実現できたりするのだ(細かい話はいろいろあるが)。
伝統的なマイコン開発の場合、マイコンの選定から開発システムの構築そしてアプリケーション開発開始まで数カ月単位の時間、そして場合によっては外部のベンダーに支払う結構な額の費用が掛かっていた。それに比べると、ほとんど初期費用と時間を掛けずにアプリケーション開発を開始できる。セキュリティ、製品安全、信頼性といった点で伝統的な開発ベンダーの牙城は崩れていないが、アイデア重視のベンチャー的な開発にはArduinoエコシステムの方が適するかもしれない。
ルネサスがArduinoにマイコンを供給?
最近、そんな「Arduino業界」にニュースが流れた。「Arduino UNO R4」にルネサスエレクトロニクスのArmコアマイコンを採用というニュースだ(Arduino.ccのニュースリリース「Arduino UNO R4 is a giant leap forward for an open source community of millions」)。近く販売開始されるらしい。
Arduino業界に詳しくない人に解説しておくと、Arduinoには仕様、形状や搭載マイコンの異なる多数の種類のボードがある。Arduino純正ボードはArduino XXX(「XXX」にはボードの名称が入る)という名を冠している。その中でも別格がArduino UNOである。このボードこそがArduinoエコシステムの中心といえるボードだ。
「XXX」の中に入る名前によっては、仕様的に少々「ハズレ」と思われるボードが存在しないわけでもない。しかしUNOはハードウェア的にも、ソフトウェア的にも中心といえる存在だ。
UNOを使っておけば、大抵のハードウェアもソフトウェアも使える標準機種なのである。そのUNO、現バージョンはR3という版である。R3にはMicrochip Technology(に買収された元Atmel)製のATmegaマイコン(RISCといいつつも8bit機)が搭載されている。ところがこのUNO R3の後継機型番のはずであるUNO R4にルネサスのArmコア製品が搭載されるというのだ。例えていえば、IBM-PCのインテル8088の後継機がインテル286でなくて、ルネサス製品になったようなものだ。
大きな一歩だが、ルネサスのマイコンがArduinoに採用されることは、既定路線ではあったのだ。何せ2022年にルネサスはArduino.ccに1000万ドル出資していたからだ。「金で買った」当然の採用とはいえ、UNOの名のもとにルネサスのマイコンが登場することは予想外だった。
欧米メーカーは小口少量に力を入れてもルネサスは……
ここでルネサスのコンシューマー分野への取り組みを簡単に振り返っておきたい。一言でいうとルネサスは「ハードルの高い」会社だった。秋葉原や通販ルートでマイコンチップやボードが買えないわけではなかったが、品種によっては正規の流通ルートの営業に登録しないとデータシートすら手に入らないことがままあった。ソフトウェアツールなども、欧米の同業他社のように無料でばらまいているというレベルとは程遠かった。
もともとマイコンビジネスはB2Bのビジネスである。1個、2個買うような客は相手にしない。数千個では試作レベル、数万個数十万個の注文をくれそうなお客になってようやくサポート対象である。
20世紀の間は欧米の会社もそんな感覚を共有していたように思われる。しかしアリゾナから現れたMicrochip TechnologyがPICマイコンを小口少量用途に「ばらまいて」市場開拓を進めたことで、みんな目を開いたのだと思う。
その後の欧米メーカーは、小口少量用途でもマイコンボードやマイコン開発ツールを誰でも手に入れられるように大衆化していった。ハードルは大きく下がったのである。
そして、中国市場が本格化するに従って、中国系の関連メーカーも巻き込んでその動きはより加速していった。そんな流れの延長に複数ベンダー相乗りでオープンな流れのArduinoがある。Arduino世界の中心にいたマイコンメーカーは当初Atmelだったが、Microchip TechnologyがAtmelを買収した。その結果、Microchip TechnologyはPICマイコンのハードルは低いが、自社で完結した世界とは別にオープンなArduino世界でも存在感を増すことになった。
一方、ルネサスというと欧米各社の大衆化を横目に「一見さんお断り」の老舗路線を墨守していた感じだ。一部コンシューマー分野に取り組みたいという動きがルネサスになかったわけではない。幾つかの取り組みの中で、今もホソボソと続いているものに「Gadget Renesas」がある。明らかにArduinoも意識した低価格な開発ボードで小口ルートを切り開こうとしたのだ。
ただし、世間に対するインパクトを見れば成功したとは言い難い。勝手な意見になるが、その裏側に多数あるマイコン系列を巡るルネサス社内での立場の違いがあるように思えてならない。大口、とくに車載などをかかえる主流製品系列の担当からしたら、情報流出も懸念される小口ルートなどに力を入れる理由は見当たらない。全社一丸となって小口ルートを推進する体制にはなかったものと想像している。
ルネサスはRISC-Vに力を入れるのではなかったの?
それがArduinoに出資してArduino UNOの名を冠する製品に搭載されることになった。Arm Cortex-M4シリーズのコアを採用した「RA4M1」シリーズのマイコンらしい。勝手に想像するに自社内で頑張っても世間の注目(特に欧州などの海外での)を集めないので、外部のArduinoに頼ったようにも見える。
そして、UNOの名はそれだけのインパクトがある。Arduino UNO R3互換の「YYYduino」(YYYには各社の名称。商標権の関係でArduinoとはうたえないので似た名前にするのだろう)といったネーミングのサードベンダー製品がどれだけあることか。
それらの多くが、今のところMicrochip Technology製品を搭載している。それらマイコンに対してプログラムを書いているアマ、プロ含めたプログラマーがどれだけいることか。その後釜にルネサスのマイコンが座れるとなったら、じわじわと影響が広がってくる可能性が高い。
一方で危惧もないわけじゃない。UNOでもR4は「ちょっと」違う、と思われて敬遠される可能性もあるからだ。同じArduinoであればいろいろ互換性が高いといいつつも、マイコンそのものが違うのだ。全く同じとはいかない。
また、ArmコアのArduinoにも敵がいないというわけではない。最初に挙げたRaspberry Piのマイコン「Pico」だ。これに採用されているマイコンはRaspberry Pi財団設計のArmコアである。なかなか従来のマイコンベンダーにはない発想のユニークなチップだ。Arduinoはオープンな環境であるため、Arduino IDEはPicoでも動作可能だ。UNO R3からR4への移行がうまくいかなければR4は仇(あだ)花となりかねない。
しかし個人的に一番気になるのがルネサス社内のArm派(?)とRISC-V派(?)の関係だ。以前、Armでは出遅れたが、RISC-Vでは先頭を切るみたいなことをルネサスの偉い人が発言していたはず。
このところのルネサスの動向をみていると、Arm搭載機種が「推し」になっている感がある。特に欧州向けでそれを感じる。その流れの中にArmコアのマイコンのArduino採用もあるように見える。
一方でRISC-Vは、用途を限ってその分野で地道に立ち上げを図っているようだ。その辺の仕切りの入れ方が、あまり昔のルネサスと変わっていないのではないかと感じる。
販売されたら、Arduino UNO R4を試してみるArduinoエコシステムの中の人々は世界中にいる。エコシステムの人々に理解できないような内向きの行動だけはしないでおいてもらいたいものだ。
筆者紹介
Massa POP Izumida
日本では数少ないx86プロセッサのアーキテクト。某米国半導体メーカーで8bitと16bitの、日本のベンチャー企業でx86互換プロセッサの設計に従事する。その後、出版社の半導体事業部などを経て、現在は某半導体メーカーでヘテロジニアス マルチコアプロセッサを中心とした開発を行っている。
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.





