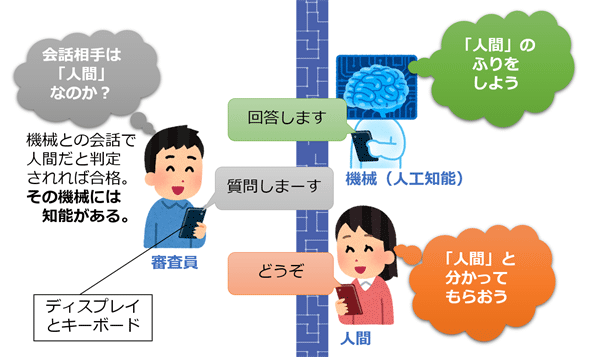チューリングテスト(Turing test)とは?:AI・機械学習の用語辞典
用語「チューリングテスト」について説明。人工知能(「機械」や「コンピュータ」とも呼ばれる)が人間をどれだけ真似られるかをテストすること。審査員は自然言語による会話を通じて、相手が人工知能か人間かを判定する。ただし、人工知能の「知性」や「知覚力(感覚を通じた情報の認識・解釈能力)」を測定するものではない。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
用語解説
チューリングテスト(Turing test)とは、機械(人工知能)の能力が、人間の「知的活動」と同等であるか、またはそれと区別がつかない程度かを確かめるためのテストである。もっと簡単に言えば、人工知能が人間を模倣し、それに人間が気付かないかをテストすることだ。ただし、このテストは人工知能の「知性」や「知覚力(感覚を通じた情報の認識・解釈能力)」を直接測定するものではなく、その人間模倣の精度を評価するためのものである。
基本的なテスト手順は次の通り。
登場人物は、図1にも示すように以下の3人である。
- 人間の審査員
- 人間のような反応をするように設計された機械(=人工知能)
- 人間
「審査員」と「機械/人間」は別々の部屋にいる状態で、コンピュータのディスプレイとキーボードを通じて自然言語の会話を行う(※元々の設定はこれだが、現代であればインターネット越しなど他の手段が取れるだろう。図1はスマートフォンを通じてチャットするイメージである)。
審査員は、機械もしくは人間(どちらか分からない)を相手に、「将棋は好きですか?」「クリスマスは何をしますか?」「東京スカイツリーを題材に川柳を詠んでください」などと、機械か人間かを判定するための質問などを行い、相手の反応を読み取る。ちなみにこの際、質問に対して機械が正しい回答を出せているかどうかは問題とされず、いかに人間に似た反応をするかだけが問題となる点に注意してほしい。
最終的に審査員は、会話相手が機械か人間かを判定する。ここでもし、機械が「人間である」と判定されるケースが多ければ(一般的には30%を超えれば)、テストに合格したことになる。合格すれば、「この機械は考えることができる」、つまり「知能を持った機械」と見なせる、というわけだ。
この方法論は、1950年にアラン・チューリング(Alan Turing)氏の論文『Computing Machinery and Intelligence』の中で提案された。チューリング氏は、「機械(=人工知能)は考えることができるのか?」という問いをやみくもに議論することは“無意味すぎる”と考え、「このようなある種のゲームをうまくこなせるか?」という問いに置き換えて議論することを提案したのである。
ただし、当然ながらチューリングテストは完璧ではない。「チューリングテストに合格したとしても、知能を持ったとはいえない」という反論がたびたび出ているのだ。その代表例には「中国語の部屋」などがある。
ここを更新しました(2023年12月4日)
チューリングテストの定義をより分かりやすく書き直しました。
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.