Webhookのベストプラクティス6選 「バッチ処理を避ける」「認証方式を合わせる」など幾つ知ってる?:プロフェッショナルのための実践ガイド
TechTargetは2025年3月7日、「Webhookのベストプラクティス」に関する記事を公開した。Webhookはシンプルなテクノロジーだ。そのため、実装計画もシンプルにする必要がある。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
TechTargetは2025年3月7日(米国時間)、「Webhookのベストプラクティス」に関する記事を公開した。
Webhookはイベント駆動型の通知ツールだ。任意のシステムやサービス、アプリケーションで発生した変更を、別のシステムに対して自動で通知する。シンプルでありながらも強力な技術であり、迅速にセットアップできると、リアルタイムでの更新が可能だ。ポーリング(定期的な問い合わせ)のような手段に比べて処理負荷が少ないという特徴もある。
本稿では、Webhookを効率的かつ効果的に、かつ安全に運用するために役立つ、6つのベストプラクティスを紹介する。
Webhookのメリット
Webhookは、システム間の通信を円滑にする手段だ。例えば、新しい作業チケットが発行されたことをIT部門に通知したり、新規の保険請求を保険会社に知らせたりする際に活用できる。さらに、Webhookには以下のような利点がある。
迅速かつ簡単なセットアップ
Webhookの構成方法は、必要なカスタマイズのレベルによって異なるが、基本的には簡単にセットアップできる。一部のベンダーは、サードパーティー製アプリケーションとの統合機能を提供している。監査対応、スケーラビリティ(拡張性)、セキュリティ機能を備えたWebhookを事前に“定義済み”の状態で提供しているため、エンタープライズ用途にも適している。
リアルタイムな更新
別のシステムに対して定期的に更新情報を照会するような処理(ポーリング)では、データ転送に遅延が生じる可能性がある。Webhookは既存のエンドポイント間で直接やりとりし、条件に合致するイベントが発生した際に自動的にAPIを呼び出す。この通知によって、ワークフロー内で追加のアクションを自動実行(トリガー)することもできる。
リソースの効率的な使用
頻繁な更新リクエストは、不要なリソース消費を引き起こす可能性があるが、Webhookは特定のイベントのみに応じて、通知するように構成されている。API呼び出しはHTTP/HTTPS経由で送信されるため、一般的にポーリングよりも処理負荷が少なくて済む。
Webhookは適切に運用すれば、システム統合および自動化のための効果的なツールになる。Webhookリクエストを変換、またはリダイレクトするために中間エンドポイントを新たに設けることも可能だが、そうした中間層の導入は、レイテンシ(遅延)の増加、処理の複雑化、さらなるセキュリティ対策の必要性を招く可能性がある。データの送信、処理、保護をより細かく制御したい場合は、APIの方が適切な通信手段となることもある。
Webhookのベストプラクティス
Webhookは、さまざまな実装シナリオに柔軟に対応できる。ここからは、構想段階から設計、導入へと進むに当たって検討すべき主要なベストプラクティスを幾つか紹介する。
「人のための」システムを構築する
Webhook導入の最適な方法は、具体的なユースケースを持つことだ。Webhookの実装を考える場合は、パフォーマンスの最適化や業務プロセスの改善を目的とすべきであり、作業を妨げるようなものであってはならない。そのため、「特定のイベントが発生した際、どのような論理的アクションをトリガーすべきか?」「既存のワークフローにどのような影響を及ぼすか?」といった問いを立てて検討することが重要だ。
例えば、Webhookによって作業チケットを自動作成してコードレビューを促す、インスタントメッセージングツールを通じてチームに通知するといったことが可能になる。しかし、イベントの発生頻度によっては、インスタントメッセージの連続通知がチームに過度な負担をかけ、業務の妨げになることもある。理論上は問題ないと思われるWebhookの実装も、実際の運用段階で期待通りに機能しないケースもある。そのため、通知手段と配信の頻度が、実際にそれを使用するチームにとって最適な形になっているかどうかを慎重に検討することが重要だ。
Webhookをテストする
短距離走者は筋肉を痛めないよう、レース前に必ず準備運動をする。同様に、Webhookのテストは「運動前のウォームアップ」と捉えるべきだ。テストすることで、Webhookが設計通りに動作するかどうかを確認できるだけでなく、問題を事前に検出、対処することで、障害の拡大を防ぐことができる。
テストは、実装上の特定の課題や関心領域に応じて設計可能だ。例えば、負荷テストを通じてスケーラビリティを評価したり、機能テストでシステムがエラーからどのように復旧するかを確認したりできる。
障害と再試行を想定しておく
どれほど優れたシステムでもダウンタイムは発生する。Webhookも、ネットワークの障害やサーバの不具合によって失敗することはあり得る。その結果、重要な情報や時間的制約のある情報が失われたり見落とされたりする可能性がある。これはWebhookが「送ったら終わり(fire-and-forget)」という性質を持っているからだ。
多くのプラットフォームでは、一定回数の自動再試行を実施する仕組みが実装されているが、信頼性と耐障害性を維持するためには、再試行ロジックや指数バックオフ(exponential backoff)のようなエラーハンドリング機能をWebhook処理の中に積極的に組み込むことが不可欠だ。
Webhookのアクティビティーをログに記録し、監視する
自動再試行は万能な解決手段ではない。例えば、Webhookが誤ったペイロード形式によって失敗した場合、再試行しても問題は解決しない可能性が高い。このような場合には、包括的なログ記録と監視の仕組みを整備し、トラブルシューティングのための情報を即座に得られるようにする必要がある。
万が一、エラーがログに記録されなかった、あるいは見逃されてしまった場合には、手作業によって監査を追加するのではなく、自動修復プロセスを設計することを検討すべきだ。これによって、人が関わる部分を極力減らして自動化できる。
バッチ処理を避ける
Webhookは、特定のイベントが発生した際に、一方向でデータを送信する軽量な仕組みとして設計されている。しかし、Webhookを使ってバッチ処理してしまうと作成されるペイロードが大きくなり、遅延の原因となる。これは、Webhookのリアルタイム性という利点が実質的に失われることになる。
また、送信するデータがファイルサイズの制限を超える場合、開発者はバッチを分割する必要が生じる。その結果、追加のコードが必要になり、処理の順序が入れ替わる、あるいはトランザクションが失敗するなどの問題が発生する可能性がある。
Webhookのセキュリティを最優先に考える
Webhookのエンドポイントは通常、インターネット上に公開されているため、攻撃や悪用の標的となりやすい。そのため、データ転送中の情報を保護するために、Webhookのセキュリティを確保するさまざまな手段が存在する。ただし、送信側と受信側のシステムの両方が、同じ認証方式をサポートしている必要がある。
最初のステップとして、脅威モデリングを実施し、潜在的な脆弱(ぜいじゃく)性やセキュリティリスクを特定するのがよい。課題が特定できれば、暗号化や相互認証といった適切な対策に対して有効な投資の判断ができるだろう。
関連記事
 「Webhookは本質的に安全ではない」 知らないと危険なリスクと対策を解説
「Webhookは本質的に安全ではない」 知らないと危険なリスクと対策を解説
TechTargetは2024年12月10日、「Webhookのセキュリティ」に関する記事を公開した。脅威からWebhookエコシステムを保護し、安全に維持するためには、Webhookを提供する側と利用する側の双方が責任を持つ必要がある。 Webhookの動作と仕組みをざっくり解説 APIとの違いとは?
Webhookの動作と仕組みをざっくり解説 APIとの違いとは?
Webhookとは、API呼び出しの基本メカニズムを有効に活用し、負荷の高い要求/応答構造によるオーバーヘッドを伴うことなく、ボタンを数回クリックするだけで、イベントのトリガーを設定する仕組みだ。 共同創業者CTOに聞いた、freeeが推進する「オープンAPI」「オープンプラットフォーム」の中身
共同創業者CTOに聞いた、freeeが推進する「オープンAPI」「オープンプラットフォーム」の中身
freeeが、同社の公開するAPIを通じたエコシステムの構築を急いでいる。これは、「オープン」の名の下に展開する単なるパートナープログラムとどう違うのか、共同創業者でCTOの横路隆氏に聞いた。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

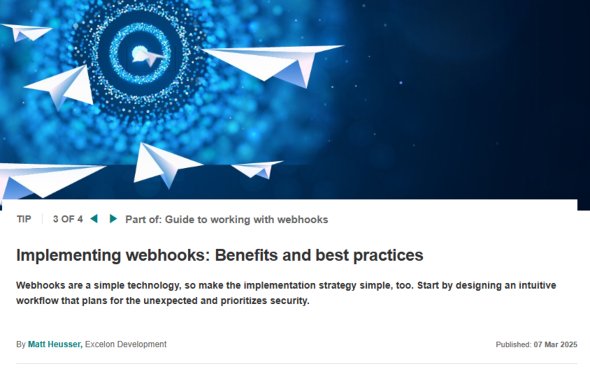 Webhookを実装するメリットとベストプラクティス(提供:TechTarget)
Webhookを実装するメリットとベストプラクティス(提供:TechTarget)



