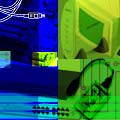|
最適ネットワーク機器選択術 3.イーサネット カード選びの方程式3-4. ノートPC用にはPCカードから選ぶ島田広道 |
|
最近では、企業向けノートPCにはイーサネット インターフェイスを標準装備するケースが増えている。こうした標準搭載のイーサネットは、ほぼすべて100BASE-TX対応であり、イーサネット ケーブルをつなげるだけで実に手軽にLAN接続が実現できる。しかし、イーサネットが標準装備されていないノートPCでは、何らかの方法でイーサネット インターフェイスを追加しなければならない。それにはPCカードかUSBを利用することになる。このうちUSB接続の詳細については、コラム「USBによるイーサネット接続」を参照していただきたい。ここでは、新旧ほとんどのノートPCで利用可能なPCカードによるイーサネット インターフェイスの実装について解説しよう。
PCカードには2種類ある
市販されているPCカードには、一般に16bit PCカード(*1)と呼ばれるものと、CardBusという2種類の規格がある。16bit PCカードとは、古くからノートPCの汎用的なハードウェア増設の手段として実装されてきた拡張インターフェイスで、ホットプラグが行えるのが大きな特徴だ。実効転送レートは1Mbytes/s〜2Mbytes/s程度なので、10BASE-T(最大1.1Mbytes/s程度)には十分だが、100BASE-TX(最大11Mbytes/s程度)の性能を活かすことはできない。一方のCardBusは、16bit PCカードの後継として規格化された拡張インターフェイスである。CardBusにはPCIの仕様を採り入れてパフォーマンスの向上を図っており、100BASE-TXの転送レートも余裕でカバーできる。
| *1 正しくない呼び方だが、16bit PCカードのことをPCMCIA対応カードなどと呼ぶこともある。PCMCIAは、PCカードの前身となった規格を策定していた団体の1つで、一時期はこの呼称をインターフェイスの識別に利用していた。しかしこれは、現在のPCカード自体を指す用語ではない。 |
16bit PCカードとCardBusの関係は、ISAスロットとPCIスロットの関係とよく似ている。ただ1つ異なるのは、CardBusは16bit PCカードの上位互換性を実現しており、CardBusのPCカード スロットには16bit PCカードも差して利用できる点だ。逆に16bit PCカードのスロットではCardBusカードは動かない。
|
||
| 2種類のPCカード | ||
| 左が16bit PCカードで、右がCardBusカード。CardBusカードのコネクタには、グラウンド接続(接地)を強化するための突起(ディンプル)が並んでいるのが分かる。 |
CardBusが最適とは限らない
性能面では16bit PCカードよりCardBusのほうが、圧倒的に優れている。しかしCardBusカードを選びたくても、選べない場合もある。1998年以降に販売されたノートPCは、ほとんどCardBusに対応しているが、逆に言えば、それ以前のノートPCでは、16bit PCカードしか利用できない可能性があるわけだ。また、初期のCardBus対応ノートPCでは、2つのPCカード スロットのうち1つしかCardBusに対応していなかったり、16bit PCカードとCardBusカードの混在が許されなかったり、PCカード スロットのモードをBIOSで16bit PCカードまたはCardBusに切り替えなければならなかったり、と制限が多かった。OSについても、Windows NTのように、標準ではCardBusに対応しないなど問題があった。
CardBusにまつわる問題は、歴史がまだ浅いことにも起因している。デスクトップPCで一般的なPCIスロットは、1992年に最初の規格が公開され、1995年ごろからPCI対応製品が普及している。すでに5年が経過し、対応製品に互換性の問題が発生するようなことがほとんどなくなっている。これに対し、CardBusは1995年に規格が公開され、1997年から対応製品の販売が始まった比較的新しい規格であるため、少なくなってきたとはいえ、未だに互換性の問題が生じることがある。
CardBusカードを購入する前には、まずPCとソフトウェアの対応をよく確認しておくべきだ。
| INDEX | |||
| [特集]最適ネットワーク機器選択術 | |||
| 1. | イントロダクション | ||
| 2. | イーサネットの基礎の基礎 | ||
| 2-1. | イーサネットの基本はCSMA/CD方式にある | ||
| コラム:IEEE802の各種規格 | |||
| 2-2. | イーサネットのフレーム形式とコリジョン ドメイン | ||
| 2-3. | 現在の主流、100BASE-TXを知る | ||
| コラム:10BASE/100BASE以外のLAN規格 | |||
| 3. | |||
| 3-1. | デスクトップPCには100BASE-TX PCIカードが最適 | ||
| コラム:できれば避けたいISAイーサネット カード | |||
| 3-2. | 一般的な100BASE-TX PCIカードの選択ポイント | ||
| 3-3. | 100BASE-TX PCIカードの付加機能をチェックする | ||
| コラム: イーサネット カードにおけるサーバ用とクライアント用の違い | |||
| 3-4. | ノートPC用にはPCカードから選ぶ | ||
| 3-5. | 100BASE-TX CardBusか、10BASE-T 16bit PCカードか? | ||
| 3-6. | PCカードならケーブルの接続方式がポイント | ||
| 3-7. | イーサネット ケーブル直結方式は便利か? | ||
| コラム:USBによるイーサネット接続 | |||
| 3-8. | デバイス ドライバは重要な選択ポイント | ||
| 3-9. | もう1つのソフトウェア サポート − ユーティリティ | ||
| コラム:Linuxのためのイーサネット カード選び | |||
| 4. | |||
| 4-1. | ハブ/スイッチの種類と機能 | ||
| 4-2. | ハブ/スイッチ選択の基礎知識 | ||
| コラム:そのほかのネットワーク機器 | |||
| 4-3. | ハブ/スイッチ選択のポイント | ||
| 「PC Insiderの特集」 |
- Intelと互換プロセッサとの戦いの歴史を振り返る (2017/6/28)
Intelのx86が誕生して約40年たつという。x86プロセッサは、互換プロセッサとの戦いでもあった。その歴史を簡単に振り返ってみよう - 第204回 人工知能がFPGAに恋する理由 (2017/5/25)
最近、人工知能(AI)のアクセラレータとしてFPGAを活用する動きがある。なぜCPUやGPUに加えて、FPGAが人工知能に活用されるのだろうか。その理由は? - IoT実用化への号砲は鳴った (2017/4/27)
スタートの号砲が鳴ったようだ。多くのベンダーからIoTを使った実証実験の発表が相次いでいる。あと半年もすれば、実用化へのゴールも見えてくるのだろうか? - スパコンの新しい潮流は人工知能にあり? (2017/3/29)
スパコン関連の発表が続いている。多くが「人工知能」をターゲットにしているようだ。人工知能向けのスパコンとはどのようなものなのか、最近の発表から見ていこう
|
|