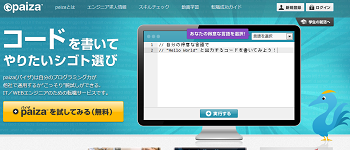Wantedly、CodeIQ、カンファレンス 本当に有効なのはどの手段?――転職2.0現状確認会:また昭和な転職で失敗してるの? きのこる先生の「かろやかな転職」(3)(3/4 ページ)
コーディング型
ポートフォリオ型の発展系として、そのものずばり「エンジニアがコードを書く」ことをコアにしたサービスもあります。エンジニアの仕事においてコードを書くという行為はかなりの比重を占めますから、登場するのも必然だったこれらのサービスを「コーディング型」と分類して見ていきましょう。
CodeIQ
「CodeIQ」は、企業の現役エンジニアが出題したコーディング問題に挑戦すると、解答を個別に添削してくれるというサービスです。
エンジニアは自分のスキルを可視化したり、解答をポートフォリオにしたりできる。企業は「問題を解く」というカジュアルな行動を通じてエンジニアにアプローチし、スキルのマッチングを行える。エンジニアと企業双方に、「転職2.0」的な転職フローを提供するサービスです。
エンジニアには「コーディング問題を見るとつい解いてしまう」という習性があるため、純粋に娯楽や腕試しとしても楽しめます。しかも現役で活躍しているエンジニアが個別に添削してくれるため、スキルアップにも効果的。コーディング問題に挑戦していたら企業の目に止まってスカウトされることもある、という「エンジニアの楽しさ」を前面に押し出したサービスです。
paiza
「paiza」は、CodeIQの対抗馬としてオープンしたサービスです。各種のコーディング問題が掲載されているのは同様ですが、こちらは採点が自動化された問題がメインで、問題を解くとランクが上がるようになっています。
実はこの「ランク」が求人に直結していて、一定のランクに到達するまで「応募不可」の求人があるなど、ちょっと挑戦的なシステムです。
他にも「オンラインハッカソン」という連作の問題に挑戦できるイベントを開催したり、「paiza learning」という動画によるプログラミング学習コンテンツを用意していたりと、エンジニアが長居して楽しんだり勉強したりできる工夫がなされています。
「コーディング型」の現状
「paiza」はもともと求人を前面に押し出したサービスで、「企業が要求するランクに到達したエンジニアが求人に応募する」というフローがメインです。一方の「CodeIQ」は、2015年8月に「CodeIQ JOBS」というスキルを軸にした求人を検索・応募できるジョブボードサイトをオープンしました。問題を解いている転職潜在層のエンジニアだけではなく、転職顕在層のエンジニアにもより積極的にアプローチしていこう、という取り組みでしょうか。
どちらのサービスも、ややもすると「エンジニアに遊び場を提供しているだけ」になってしまう危惧があります。しかし、採用面接の際にコードテストをする企業も増えていますし、応募の際に「応募してきたエンジニアがどんなコードを書くのか」を把握できるのは、企業にとって大きなメリットです。
菌類は採用担当として、「コーディング型」の展開に注目しています。もちろん、エンジニアがコーディング問題で遊んでいるうちにスキルアップするのはソフトウエア開発業界全体にとってのメリットですので、こちらの効果も期待しています。
関連記事
 友達以上転職活動未満?――カジュアルな会社訪問のススメ
友達以上転職活動未満?――カジュアルな会社訪問のススメ
プログラマーにしてWeb系企業の採用担当の「きのこる先生」が指南する、転職サービスに依存せずソーシャルなつながりを活用する「転職2.0」の活用法。今回は、求人企業側から見た旧来の採用方法の問題点と、それを是正するために登場した「Wantedly」の概要を紹介しよう エンジニア兼採用担当者が、古今東西エンジニアの転職事情をひもトーク
エンジニア兼採用担当者が、古今東西エンジニアの転職事情をひもトーク
元プログラマー、現Web系企業の人事担当者「きのこる先生」が帰ってきた! 転職サービスに依存せずソーシャルなつながりを活用する「転職2.0」で、エンジニアは幸せな転職ができるのか? 職歴書も、エージェントも使わない転職も、あるんだよ
職歴書も、エージェントも使わない転職も、あるんだよ
今回は「転職エージェントを使わない転職」をテーマに、「ラブレターのいらない告白」と「愛の伝え方」を紹介します ウォンテッドリーの人材自体がWantedlyサービスの最たる成功事例──プログラマーCTOの挑戦
ウォンテッドリーの人材自体がWantedlyサービスの最たる成功事例──プログラマーCTOの挑戦
CTOとは何か、何をするべきなのか――日本のIT技術者の地位向上やキャリア環境を見据えて、本連載ではさまざまな企業のCTO(または、それに準ずる役職)にインタビュー、その姿を浮き彫りにしていく。第4回は「人と企業とのマッチング」を支援するビジネスSNS「Wantedly」の提供で急成長を遂げているウォンテッドリーのCTOでプログラマーの川崎禎紀氏に話を伺った もはや履歴「書」ではない〜Re.vu(レ・ビュー)の使い方:登録編
もはや履歴「書」ではない〜Re.vu(レ・ビュー)の使い方:登録編
海外Webサービスの使い方を「日本語で」分かりやすく説明するシリーズ。今月はオンラインプロフィールページ作成サービス「Re.vu(レ・ビュー)」を紹介します LinkedInの情報を3秒でコンパイル〜Kinzaa(キンザー)の使い方:レジュメ作成編
LinkedInの情報を3秒でコンパイル〜Kinzaa(キンザー)の使い方:レジュメ作成編
海外Webサービスの使い方を「日本語で」分かりやすく説明するシリーズ。本日は一から手入力したり、「LinkedIn(リンクトイン)」の情報を基にしたりして「Kinzaa(キンザー)」でレジュメを作成する方法を紹介します
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.