| Linux Tips | |
|
NTFSパーティションにアクセスするには 北浦訓行 |
|
カーネル2.4では、Windows NT/XPのNTFSをサポートしている(ただし、リードオンリー)。しかし、Red Hat Linux 7.3などではNTFSサポート機能がデフォルトではオフになっている(Vine Linux 2.5およびTurbolinux 8 Workstationはデフォルトでアクセス可能)。そこで、Red Hat Linux 7.3を例に、NTFSパーティションにアクセスするための設定(カーネルの再構築)を行う。
最初に、rootでログインしてカーネルのソースがあるディレクトリに移動する。
# cd /usr/src/linux-2.4 |
次に、Makefileを編集する。念のためMakefileのバックアップを作成してから、テキストエディタでMakefileを開いて以下を変更する。
# export INSTALL_PATH=/boot |
|
↓
|
export INSTALL_PATH=/boot |
EXTRAVERSION = -5custom |
|
↓
|
EXTRAVERSION = -5ntfs ←NTFS用の変更を加えたカーネルであることが分かるようにする |
続いて、設定の初期化とカーネルに組み込むコンポーネントの指定を行う。
# make mrproper ←設定を初期化 |
デフォルトの設定ファイルは/usr/src/linux-2.4/configsにあるのだが、PCによって内容が異なっている。例えば、CeleronやPentium 4などの場合は、kernel-2.4.18-i686.configを選択する。ログイン時に画面に表示されるカーネルなどのメッセージに、必要な情報が含まれているので参考にするといい。例えば筆者のPCでは、
Red Hat Linux release 7.3 (Valhalla) |
と表示されるので、カーネルのバージョンは2.4.18-5で、CPUのタイプはi686だと分かる。
# make xconfig |
を実行すると、カーネルの設定ウィンドウが表示される。
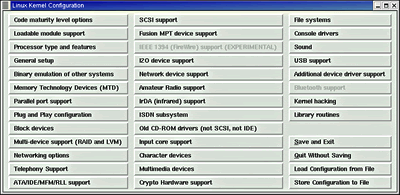 |
| カーネル設定画面 |
右上にある[File systems]ボタンをクリックすると新しいウィンドウが開くので、[NTFS file system support]の[m]を選択する。
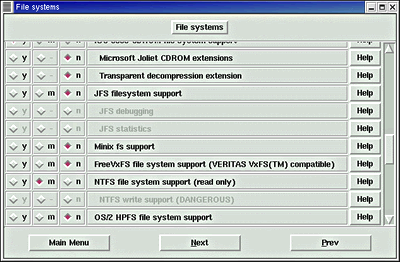 |
| [NTFS file system support]の[m]を選択する |
それが終わったら[Main Menu]ボタンをクリックしてメインメニューに戻り、[Save and Exit]ボタンをクリックしてからウィンドウを閉じる。
カーネルの再構築作業を続ける。
# make dep ←includeファイルの依存性チェック |
以上で、カーネルの再構築作業は終了だ。
ちなみに、make installを実行するとgrub.confも自動的に作成され、新しいカーネルと古いカーネルの両方で起動できるようになる。GRUBのメニューには、従来の[Kernel 2.4.18-5]のほかに[Kernel 2.4.18-5ntfs]が表示されるはずだ。そこで、[Kernel 2.4.18-5ntfs]を選択して[Enter]キーを押す。
新しいカーネルで再起動したら、以下のコマンドでNTFSパーティションをマウントしてみよう。
# mkdir /mnt/ntfs ←マウントポイントを作成 |
注意:カーネル再構築の際、設定が不適切であったりするとシステムが起動しなくなる恐れがあるため、作業は細心の注意を持って行う必要がある。また、万一システムが起動しなくなったときのために、起動ディスクを用意しておくことをおすすめする。作成していない場合は、「ブートディスクを作成するには」を参照。
| Linux Tips Index |
| Linux Squareフォーラム Linux Tipsカテゴリ別インデックス |
|
- 【 pidof 】コマンド――コマンド名からプロセスIDを探す (2017/7/27)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、コマンド名からプロセスIDを探す「pidof」コマンドです。 - Linuxの「ジョブコントロール」をマスターしよう (2017/7/21)
今回は、コマンドライン環境でのジョブコントロールを試してみましょう。X環境を持たないサーバ管理やリモート接続時に役立つ操作です - 【 pidstat 】コマンド――プロセスのリソース使用量を表示する (2017/7/21)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、プロセスごとのCPUの使用率やI/Oデバイスの使用状況を表示する「pidstat」コマンドです。 - 【 iostat 】コマンド――I/Oデバイスの使用状況を表示する (2017/7/20)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、I/Oデバイスの使用状況を表示する「iostat」コマンドです。
|
|




