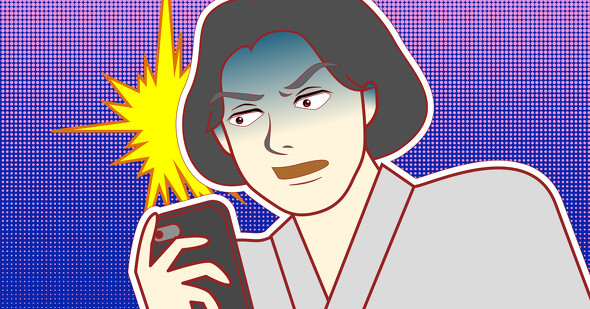これは左遷ではない、慰労だ:コンサルは見た! 偽装請負の魔窟(10)(2/3 ページ)
創業社長の戦略
そのころサンリーブス社長の布川は、箱根のホテルでくつろいでいた。
既に1週間、長年の疲れをとることに専心していた。サンリーブスを立ち上げてから10年、会社の時価総額は創業時に比べれば数十倍になっており、自社株を大量に保有する布川の資産は10億円ほどに膨らんでいた。
「こんなもんだろう」――布川は手に持ったグラスを傾けながらつぶやいた。
サンリーブスをさらに成長させるつもりはない。とにかく会社の時価総額を上げ、株価をつり上げて売り抜ける。創業当初からそれしか考えていなかった。一緒に会社を立ち上げた2人のエンジニアは、そんな経営方針に反発して出ていったが、それはそれで構わない。彼らは株価を上げるのに貢献してくれたし、株を売り抜けるタイミングでは、あの2人がいない方が面倒がない。
創業メンバーだった志村と加藤は、AI(人工知能)とRPA(ロボティックプロセスオートメーション)の分野で国内指折りのエンジニアだ。大手ITベンダーの社員だった2人が管理職になるのを嫌って退職し、フリーでエンジニアをしていたところに布川はAIのベンチャーを立ち上げたいと話を持ち掛けた。2人がいる会社ということで、彼らにあこがれるエンジニアが何人も集まってくれたし、育ってもくれた。
しばらくは志村と加藤に思い通りの研究とプロダクト開発をさせていたが、それは一種のプレゼンテーションだった。資金にも限界がある布川は、しばらくすると請負仕事を取り、エンジニアたちを顧客に常駐させた。仕事は何でも構わない。AIやRPAと無関係でもいい。とにかく人を動かせば、金が入ってくるのだ。
志村と加藤の作るAIソフトウェアは、大ヒットとまではいえないが、一応商品としては成り立つ程度に売れていた。それをサンリーブスの表看板とし、実際には人材派遣業に近い形でエンジニアをユーザー企業に常駐させる。そして客に「社員たちを好きに使ってくれ」と耳打ちする。どれだけ残業させようと、成果物の完成責任を負わせようと構わない。とにかく便利に使ってくれ、というだけだ。
優秀な志村と加藤に育てられたやはり優秀なエンジニアたちを好きに使えるとあって、サンリーブスの顧客からの評判は良く、順調に業績を伸ばし、株価も上昇した。
しかし、そうした不誠実な雇用は長くは続かない。いずれはエンジニアたちも嫌気がさして辞めていくだろうし、イツワのプロジェクトでは問題が起きているようだ。そろそろ、株を売り抜けて多額の現金を手にする時期だろう。その後、会社や社員たちがどうなったところで、もう自分には関係のないことだ。布川はスマートフォンでサンリーブスの株価を確認した。
2700円――日本時間の午前終値だ。
関連記事
 コンサルは見た! 偽装請負の魔窟(1):口うるさいプロマネはチェンジだ!
コンサルは見た! 偽装請負の魔窟(1):口うるさいプロマネはチェンジだ!
システムと人間のトラブル模様を描く「コンサルは見た!」。Season5(全11回)は「偽装請負」が招く悲劇を描きます。美咲と白瀬は、心身ともにボロボロになっていくエンジニアたちを救えるのか――? YOU、読んじゃいなよ――小説で学ぶシステム開発トラブル解決法「コンサルは見た!」、待望の電子書籍化
YOU、読んじゃいなよ――小説で学ぶシステム開発トラブル解決法「コンサルは見た!」、待望の電子書籍化
人気過去連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する@IT eBookシリーズ。第43弾は「コンサルは見た! Season1 与信管理システム構築に潜む黒い野望」。粗い要件定義書、荒ぶるユーザー担当者、銀行業務に明るくないシステム開発会社――箱根銀行のシステム開発プロジェクトのトラブルを若手コンサルタントが解決する痛快IT小説だ AIシステム発注に仕組まれたイカサマを美人コンサルは見抜けるのか?!――システム開発トラブル小説「コンサルは見た!」、Season2が早くも登場
AIシステム発注に仕組まれたイカサマを美人コンサルは見抜けるのか?!――システム開発トラブル小説「コンサルは見た!」、Season2が早くも登場
人気過去連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する@IT eBookシリーズ。第45弾は、「コンサルは見た!」シリーズのパート2が早くも登場。正式契約をにおわせて無料でプロトタイプを作らせた揚げ句、AIの学習データまで奪った悪徳顧客。だまされたシステム開発会社は泣き寝入りするしかないのか――? コンサルは見た! 情シスの逆襲(1):裏切りの情シス
コンサルは見た! 情シスの逆襲(1):裏切りの情シス
小塚と羽生――同期入社の2人を引き裂いたのは、大手高級スーパーのIT化を巡る政治と陰謀だった。「コンサルは見た!」シリーズ、Season4(全12回)のスタートです コンサルは見た! オープンソースの掟(1):ベンチャー企業なんて、取り込んで、利用して、捨ててしまえ!
コンサルは見た! オープンソースの掟(1):ベンチャー企業なんて、取り込んで、利用して、捨ててしまえ!
ソースコードを下さるなんて、社長さんたらお人よしね――「コンサルは見た!」シリーズ、Season3(全9回)のスタートです
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.