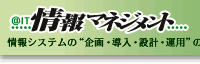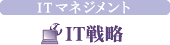| ■ワークスタイル |
| エンタープライズ2.0――次世代ウェブがもたらす企業変革 | ||
| ●吉田 健一=著 ●インプレスR&D 2007年8月 ●1800円+税 978-4-8443-2449-2 |
||
| Web 2.0の手法を使い、企業に大きな変革をもたらす「エンタープライズ 2.0」。本書は、その本質的な変化や具体的なテクノロジとは何か、そしてワークスタイルや企業経営はどのように変わっていくかを解説する。 エンタープライズ 2.0が解決する経営課題の1つが、集合知によりワークスタイルの変革だ。ナレッジマネジメントは、ナレッジ=データという「データ中心」なとらえ方により下火になったが、集合知の場合は「ユーザー参加型」という点に特徴がある。この「人中心」のアプローチは、これまでの「データ中心」のアプローチと異なり、集合知の考え方を取り込んだナレッジマネジメントによる真の経営課題の解決を実現する。 急務になっている情報系システムのシステム間相互連携では、マッシュアップがシステム間の「相互運用性(インターオペラビリティ)」の課題を解決する。また、めまぐるしく変わる経営環境に合わせて、スピーディかつ低コストで新しいシステムを提供したいといった「柔軟性(フレキシビリティ)」や、既存システムの有効活用の点でも有効だ。「SaaS」などの社外サービスを必要に応じて使うほか、情報系システムを1つにまとめて表示する「マッシュアップポータル」や分散したシステムから必要な情報にアクセスする「エンタープライズサーチ」がシステム間相互連携の解となる、という。 これまでの流れから今後どうなっていくかまでを具体例を挙げて説明するほか、Web 2.0を代表するサービスやエンタープライズ 2.0を担う技術についても詳しい。図表やキャプチャが多く、難解な言葉には解説が加えられているため情シス部門の人々だけでなく、経営者にもお奨めしたい。(ライター・生井俊) |
||
| SaaSはASPを超えた | ||
| ●北原 佳郎=著 ●ファーストプレス 2007年9月 ●1500円+税 978-4-903241-62-3 |
||
| 企業の要求に合わせてカスタマイズされたソフトウェアの機能を、ネットワーク経由で利用するサービス「SaaS」。ソフトウェアを所有するのではなく、利用するという流れの中でSaaSの力をどのように見極め、どう経営に生かすべきかを本書では紹介する。 SaaSがユーザー企業の経営に与える最大のインパクトは、負荷の発生を抑えることが可能になることだ。負荷とは、ソフトウェアのインストールやバージョンアップ対応といったヒトという経営資源の消費、サーバや電源、インターネット回線といったモノの準備などのことで、SaaSであれば新たに発生する負荷がほとんどない。導入時のキャッシュアウトが不要で、変化に迅速に対応可能、固定資産とみなされず、導入期間が短いなどのメリットがある。 ベンダがSaaSビジネスを成立させるための要素として、「マルチテナント」「カスタマイズ性」「ユーザーインターフェイス」の3つを挙げる。マルチテナントとは、1つの枠組みの中に複数組のビジネスルールを設定できる仕組みのこと。1つの枠組みに対し、1組のビジネスルールしか設定できないASPとはこの点が異なるとする。また、カスタマイズという言葉の定義がまちまちだが、先駆的なSaaSベンダは「機能」「時間」「保守性」の3条件をクリアしてきた、という。 本書はソフトウェアの利用にとどまらず、これを使って業務プロセスを外部化するSaaS+BPOの形態にも触れる。専門用語がほとんどないため読みやすく、ITシステムの在り方を検討している経営者やマネージャにお奨めだ。(ライター・生井俊) |
||
| 知的創造のワークスタイル──来るべきユビキタス社会における新しい働き方の提案 | |||||
| ●次世代オフィスシナリオ委員会=編 ●東洋経済新報社 2004年12月 ●2000円+税 4-492-76153-5 |
|||||
| 情報通信分野の急速な進展に伴い、ホワイトカラーのワークプレイス(オフィス)は根本的な改革が求められている。これからのオフィスは「知の交流・共通点」であり、専門家の「コラボレーション」の場として機能する。本書はその中で「生産性改善」と「価値(知識)創造」の可能性を追究していく。 4部構成で、第1部では4名の専門家が「ユビキタス社会における新しい働き方」についてまとめている。21世紀の企業に求められるのは、効率性追求から創造性追求への転換で、学習する組織であることが望ましい。その組織で経営者は、「ビジョンを明確に示す」「ワーク環境を整える」「スチュワード(執事)の仕事をする」役割を担う(日本テレコム・倉重英樹社長の項より)。 第2部「ユビキタスコラボレーションの提案」では、現状のオフィスの検証を行い、次世代のワークスタイル例を示す。ワークプレイスは多様化しており、時間や場所にとらわれずナレッジワークをサポートする場が求められている。そこから、コラボレーションによるナレッジリアクター(知の沸騰)が起こることを目指す。 働く「場」についての理想を追求した本書は、前向きな仕事を生み出すためにも役立つ。経営者やマネージャには本書を参考に、次世代のワークスタイルを創り出してほしい。(ライター・生井俊)
|
|||||
| 各書評にある |
@IT情報マネジメント 新着記事
この記事に対するご意見をお寄せください managemail@atmarkit.co.jp
キャリアアップ
転職/派遣情報を探す
「ITmedia マーケティング」新着記事
「サイト内検索」&「ライブチャット」売れ筋TOP5(2025年5月)
今週は、サイト内検索ツールとライブチャットの国内売れ筋TOP5をそれぞれ紹介します。
「ECプラットフォーム」売れ筋TOP10(2025年5月)
今週は、ECプラットフォーム製品(ECサイト構築ツール)の国内売れ筋TOP10を紹介します。
「パーソナライゼーション」&「A/Bテスト」ツール売れ筋TOP5(2025年5月)
今週は、パーソナライゼーション製品と「A/Bテスト」ツールの国内売れ筋各TOP5を紹介し...