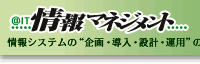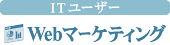| ■ネットビジネス |
| 大企業のウェブはなぜつまらないのか──顧客との対話に取り組む時機と戦略 | ||
| ●本荘 修二=著 ●ダイヤモンド社 2007年2月 ●1600円+税 978-4-478-00022-0 |
||
| ネットの世界では、大企業の組織力が発揮されにくく、顧客の期待に応えていない現状がある。本書はこのような課題の構造を明らかにし、何をなすべきかを示したものだ。 「日本人は、どこまでネット化するのか」、これは企業がネットの影響を考えるに当たって最も基本的な質問だが、意外と人々の認識には差がある。一部にはネット普及懐疑論も聞かれるが、日本人の約6割がすでにネット化しているため、大勢は決したと見られる。ただし、B to Cに関しては3.5兆円(2005年)で、eコマース率はまだ1.2%にすぎないという冷ややかにならざるをえないデータがある。 既存メディアとネットがどう付き合うべきかについては、対立ではなく融合する方向にあると説く。すなわち、メディア全体で考えると消費者が広告を避ける傾向が強まっており、この危機的状況に対してクロスメディア、顧客にかかわるビジネスプロセスの融合という方向が見えるという。これは既存のメディアの地位が下がるのではなく、新たなメディアであるネットの地位が上昇するととらえるのが妥当だ。全般的なメディア効率低下に対して、大企業の事業活動の方向として「メディアの組み合わせ」が鍵になる。経済学者のシュンペーターは「イノベーションは新結合から生まれる」と教えたが、この状況はまさにそれに当たる、と解説する。 Web2.0の影響度から始まり、変わる顧客の姿、大企業のネット化に必要なロードマップ、ネット化に取り組む推進力など、さまざまなテーマに触れている。内容に目新しさはないが、このあたりをさらっておきたいマネージャ向けの本だろう。(ライター・生井俊) |
||
| アマゾンのロングテールは、二度笑う──「50年勝ち残る会社」をつくる8つの戦略 | ||
| ●鈴木 貴博=著 ●講談社 2006年10月 ●1600円+税 4-06-282031-5 |
||
| 「会社の寿命は30年」といわれるが、自社が戦うのに都合のよい市場を選ぶ「戦略力」により、50年たっても勝ち残る企業であり続けることができる。本書では、ロングテールをはじめとする経営戦略を、大企業の成功・失敗例から解説する。 第1章では、イトーヨーカドーの凋落から、同社のビジネスとそれを取り巻く環境について説明する。イトーヨーカドーには数々の「優秀な仕組み」とグループ内の「優良企業」が存在するが、それでもGMS(大型量販店)という本業のライフサイクルが終盤に差し掛かっている。著者は、このような衰退事業をコア事業に定めたまま、工夫を重ねて難局を乗り切ろうとする安易な戦略に警鐘を鳴らす。 第7章では、タイトルにもなっているアマゾンのロングテールを扱う。Web 1.0時代にひとり勝ちしたインターネット企業のアマゾンが、Web 2.0の時代になり、ロングテールの威力を発見したことで、再び大笑いすることになったと説く。それがなかった時代に比べ2倍のROAを叩き出しているが、実は売り上げの3分の1は無在庫販売が生み出すもので、利益があがるのは当然だという。 戦略を学術的に解説するのではなく、これまでのビジネスで成功・失敗した企業の分析を通じ、戦略が持つ意味合いを学ぶ1冊になっている。(ライター・生井俊) |
||
| ロングテール──「売れない商品」を宝の山に変える新戦略 | ||
| ●クリス・アンダーソン=著/篠森 ゆりこ=訳 ●早川書房 2006年9月 ●1700円+税 4-15-208761-7 |
||
| 文化を席捲する大きな箱(ヒット作品)への需要はまだあるが、それが唯一の市場ではなくなった。ヒット市場は、いまやあらゆる大きさの無数のニッチ市場と競い合い、消費者はもっとも選択肢の多いところに引き寄せられる時代になった。その「マルチ市場」が本書のテーマだ。 オンライン音楽配信サービスを展開する「Rhapsody」は、現在150万曲を超える曲を提供している。同サイトの月ごとの売上統計値をグラフにすると、ほかのレコード店とよく似た曲線が得られる。しかし、ここ1世紀の間、注目され続けていた曲線の左側(売れ筋)ではなく、逆に右側に目を向けると2つのことが分かる。1つは曲線はゼロにはならないということ、そしてもう1つは売れない曲はわんさとあるので、足すと大した額になる。このグラフの右に伸びる長いしっぽが「ロングテール」だ。 ロングテール時代到来に向けて、3つの追い風が吹いている。1つ目は「生産手段の民主化」で、パソコンを使っていまや誰もが印刷機、撮影所、音楽スタジオなど何でも手に入れられる。2つ目は「流通手段の民主化」で、インターネットによってみんなを卸業者にした。3つ目は「需要と供給の一致」で、検索エンジンやアフィリエイトなどが消費者に新商品や珍商品を紹介するようになり、テールに需要を呼び寄せることができるようになった。これらの追い風がロングテール市場での新たなビジネスチャンスを生む、と説く。 ロングテールが生まれた背景や米国でのヒットビジネスの変遷などを、事例を通じてていねいに解説する。物語としても楽しめ、特に新しいビジネスの創出に関わる部門やプロジェクトマネージャにオススメしたい。(ライター・生井俊) |
||
| Eビジネスの経済学──ドットコム危機後のIT経済 | ||
| ●F・G・アダムス=著、熊坂侑三=訳 ●日本評論社 2005年12月 ●2500円+税 4-535-55393-9 |
||
| 経済を変革するようなEビジネス革命は果たしてあったのか──。この疑問に答えるため、本書では事例やデータから「ニューエコノミー」や「Eビジネスとは何か」を掘り下げ、従来の経済理論との違いをまとめる。 コミュニケーション手段を例にとれば、オールドエコノミーとニューエコノミーではまったく異なる。これまでは、人同士、あるいは電話でお互い接触をしていたのだが、いまではEメールを通しての接触が増えている。より重要なのは、多くの人同士の接触がなくなっているということだ(partII-5)。 Eビジネスにおいて、うまくいった例を考えると、最も成功し長く続いているベンチャーには、Eトレードのようにユーザーのコスト削減につながったり、アマゾン・コムのように商品選択の範囲や便利さに大きな改善が見られるといった点が必ず含まれる。一方、うまくいかないのは、すべての購入者がWebに移行するという考え、プログラムや選択プロセスが複雑といった問題点があるという(partII-10)。 結論的には、ニューエコノミーが存在するのかについて定義によりどちらとも解釈できるとしている。事例や統計資料が豊富で、ITバブル崩壊以降の流れを振り返り、冷静に見直してみるうえで大いに参考になる。(ライター・生井俊) |
||
| 「顧客の声」は本当にビジネスに役立つのか? ──小さな会社でも大企業を動かせるツール=ネット・コミュニティ |
||
| ●藤田憲一=編、ジェイ・マーチ=著 ●中央経済社 2004年3月 ●1800円+税 ISBN4-502-37250-1 |
||
| 30代の主婦層に人気がある地域情報交換サイト「とくっち.com」を運営する著者が、ネット・コミュニティ論を説く。これまでコミュニティサイト運営者やSEらが経験や勘で構築、運営してきた部分を平易な文章で表現しており、具体例が豊富に盛り込まれている。 ECサイトの売上最大化のためには、ユーザーの訪問回数を増やす必要がある。そのために、モールへ出店したり、バナーやメールによる広告、アフィリエイトなどの方法もあるが、アクイジション(新規顧客獲得)のコストが掛かるだけでなく、定着化させるために特売やポイント加算プログラムなどを行えば、値引き競争に陥る可能性がある。それに対してコミュニティを導入すると、価格的なインセンティブなしに訪問回数の増加や、サイトのブランディングに効果的だという(第3章)。 では、コミュニティサイトを構築するにはどうすればよいのだろう。そこには「ミッションの決定」「ビジョン、ポジションの策定」「運営方針の決定」などのプロセスがある。その中でも、コミュニティでの体験がユーザーのロイヤリティを引き出し、価値を創造する書き込みが行われる雰囲気や仕組み作りにつながる「ユーザー環境デザイン」が大事になる。そこには、導線設計だけでなく、ユーザー体験の「質」を高める努力が必要だと説明している(第4章)。 全体的には、ネットやITに詳しくない経営者などでも読めるように書かれているが、コミュニティに詳しい方は、第3章や第4章あたりから読み進めてもいいだろう。(ライター:生井俊) |
||
| 各書評にある |
Webマーケティング 新着記事
@IT情報マネジメント 新着記事
この記事に対するご意見をお寄せください managemail@atmarkit.co.jp
転職/派遣情報を探す
「ITmedia マーケティング」新着記事
「サイト内検索」&「ライブチャット」売れ筋TOP5(2025年5月)
今週は、サイト内検索ツールとライブチャットの国内売れ筋TOP5をそれぞれ紹介します。
「ECプラットフォーム」売れ筋TOP10(2025年5月)
今週は、ECプラットフォーム製品(ECサイト構築ツール)の国内売れ筋TOP10を紹介します。
「パーソナライゼーション」&「A/Bテスト」ツール売れ筋TOP5(2025年5月)
今週は、パーソナライゼーション製品と「A/Bテスト」ツールの国内売れ筋各TOP5を紹介し...