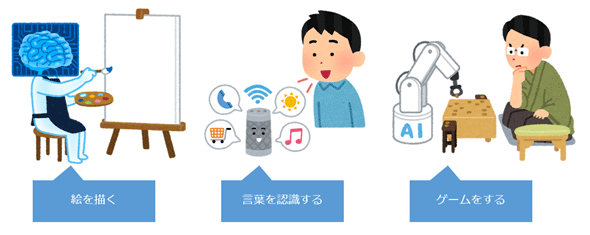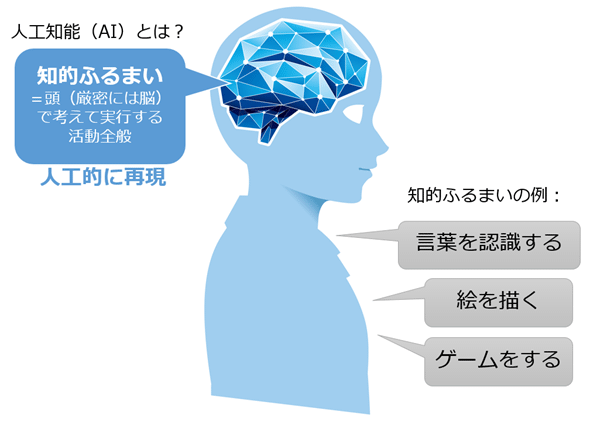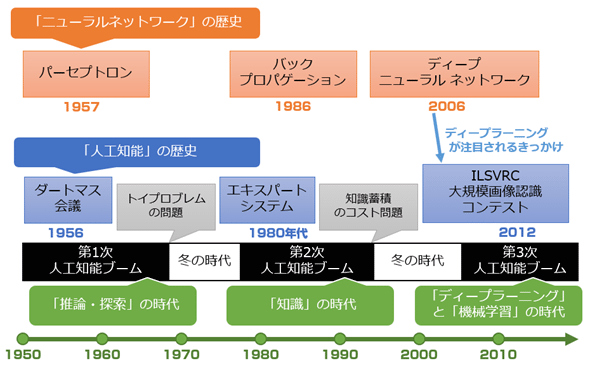人工知能(AI:Artificial Intelligence)とは?:AI・機械学習の用語辞典
用語「人工知能」について説明。人間が行う「知的活動」をコンピュータプログラムとして実現することを指す。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
用語解説
人工知能(AI:Artificial Intelligence)とは、人間が行う「知的活動」をコンピュータプログラムとして実現すること。知的活動とは、頭(厳密には脳)で考えて実行する活動全般のこと。例えば「絵を描く」「言葉を認識する」「ゲームをする」などなど、あらゆる人間の行動がこれに当てはまる(図1)。
近年、人工知能の一種として注目を集めているのが、機械学習である。
より詳しい解説
機械学習とは、データから学習することで、適切な知的ふるまいを人工的に実現すること、もしくはその研究分野を指す。人間は、経験から学ぶことによって適切な知的ふるまいが行えるようになる、と考えられる。例えば、リンゴやミカンなど何度もフルーツを見ることによって、フルーツの種類を見分けられるようになる。機械学習も同じで、データから学ぶことによってフルーツを識別できるようになる。
その機械学習の一手法として大注目されているのがディープラーニング(深層学習)である。2010年代以降に急速に人気を高め、「第3次」と呼ばれる新たな人工知能ブームを巻き起こしている。ディープラーニングは、画像認識(例えば画像からの犬や猫などの判定)や音声認識、さらには自動運転技術と、さまざまな分野への応用が始まっており、今後もさらに発展することが期待されている。
以下では、幾つかの観点から、人工知能をできるだけ簡潔に説明する。
1. 人工知能の定義
1.1 さまざまな定義内容
一般的に認識されている人工知能の意味は上述の通りであるが、それを厳密に定義する文章があるわけではない。人によって、さまざまな定義を行っている。表1では、その中でも分かりやすい定義を幾つかまとめた。
| 定義 | 人物 |
|---|---|
| 人工的につくられた人間のような知能、ないしはそれを作る技術 | 松尾 豊(東京大学大学院 工学系研究科准教授) |
| 人工的につくられた、知能を持つ実態。あるいはそれをつくろうとすることによって知能自体を研究する分野である | 中島 秀之(公立はこだて未来大学学長) |
| 人間の頭脳活動を局限までシミュレートするシステムである | 長尾 真(京都大学名誉教授、前国立国会図書館長) |
| 主な人工知能の定義(引用:『深層学習教科書 ディープラーニング G検定(ジェネラリスト) 公式テキスト』の一部、出典:『人工知能学会誌』) | |
1.2 ロボットと人工知能の違い
人工知能の一般的なイメージとして、ロボットと混同されることが多い。その違いをあらためて、明確にしておこう。
人工知能は、人間における「脳」に相当するものだと言える。それに対してロボットは、人間における「体」に相当するものだと言える。
もちろん、脳が体の一部であるように、人工知能がロボットの一部として活用されるケースもある。ただし、そうではない、体=ロボットを持たない人工知能の方がより多く活用されている状況だ。
人工知能は、あくまで「知的ふるまい」を中心に据えた分野であり、ロボット内で使われるかどうかは、別の問題であることに留意してほしい。
2. 人工知能の大分類
人工知能は、実現容易度の面からは、「強いAI」と「弱いAI」(ジョン・サール氏、1980年)という2つに大きく分類されることがある。それぞれの意味を説明する。
2.1 強いAI = 汎用型AI
強いAI(Strong AI)とは、人間が行う知的活動を完全に模倣できるAIで、「汎用(はんよう)的なAI」(AGI:Artificial General Intelligence)とも表現される。対義語に、弱いAIがある。
例えば、人間のように考えて行動できる「ドラえもん」が、まさに「強いAI」である。つまり心を持つ人工知能のことである。
しかし現在の技術は、まだ「強いAI」を実現できるレベルまでには進んでいない。現在の機械学習やディープラーニングで実現されているAIは、「弱いAI」とされる。
2.2 弱いAI = 特化型AI
弱い(Weak AI、Narrow AI)とは、特定の処理のみを実現するAIで、「特化型AI」とも表現される。心を持たない、有用な道具として使われる人工知能のことである。対義語に、強いAIがある。
例えば、工場で製造される製品の中から不良品を見分ける処理は、「弱いAI」である。この処理は不良品が見分けられるだけで、人間のように汎用的に何でもできるわけではない。
現在の技術レベルは、この「弱いAI」を実現している段階である。弱いAIを組み合わせることで汎用性を高めれば、「強いAI」が実現できるのではないかという期待もあり、研究が続けられている。
3. 成果・事例
人工知能で成果が出ている事例を紹介しよう。特にディープラーニング手法において「画像認識/生成」「音声認識/生成」「自然言語処理」「ロボティクス(強化学習)」などの分野で大きな成功事例がある。その中でも「画像認識」の応用事例は豊富で最も成功しており、今後もさらに躍進することが期待される。なお、各事例は必ずしも1つのAI技術とは限らず、複合的な先進技術の組み合わせの場合が多いので、その点は留意してほしい。
3.1 画像認識/生成に関する主な事例
- 物体認識: 犬や猫の識別や、物体の意味の言語化など
- 不良品の検出: 製造業で作る部品(例えば車のねじ)などの検品など
- 異物混入の検出: 食品の製造ラインでの異物検出など
- 病変の検出: レントゲンなどの医療画像から病変を見つけるなど
- 自動運転: 現在、産業界で競争が激化している
3.2 音声認識/生成に関する主な事例
- スマートスピーカー: Google HomeやAmazon Echoなど、音声で問い掛けると、何らかの回答を話す製品
3.3 自然言語処理に関する主な事例
- チャットbot: Webサイト上で質問が投稿されると、それに対する適切な回答を自動的に返すことで、会話を成立させるもの。例えば女子高生AI「りんな」
3.4 ロボティクス(強化学習)に関する主な事例
- ゲームの自動対戦: 2015年に人間のプロ囲碁棋士をAIが破ったとして有名になった。例えばAlphaGo(アルファ碁)
4. 主な歴史
1950年ごろから始まった人工知能の研究は、10〜20年単位で「ブーム」と「冬の時代」が交互に訪れた歴史を持つ(図3)。なお、ブームや冬の時代に明確な区切りがあるわけではないので、あくまで以下はざっくりとした時代区分けとなっていることに注意してほしい。
各ブームについて内容を簡単に紹介しよう。
4.1 第1次人工知能ブーム
1956年、ダートマス会議で、ジョン・マッカーシー氏により「人工知能」という名前が提示され、これをきっかけに新たな研究分野が生まれたとされる。その後、1957年に「パーセプトロン」という、ニューラルネットワークの基盤となる概念が公案されるなど、人工知能、特にニューラルネットワークに関する研究が活発となった。
これが「第1次人工知能ブーム」である。この時代のAI研究の中心は、主に「(迷路やパズル、数学定理の証明などの)推論・探索」に関するものであった。
しかし1960年代に入ると、単純なパーセプトロンの限界、具体的には線形分離不可能なパターンを識別できないこと(マービン・ミンスキー&シーモア・パパート氏、1969年)などが示されるなど、パーセプトロンでは簡単な問題しか解けないこと(「トイプロブレムの問題」と呼ばれる)が明らかになった。このため、1970年の前半からは、AI研究の人気が下火になる「冬の時代」へと突入していく。
4.2 第2次人工知能ブーム
1980年代に入ると、医療など特定分野の知識を蓄積しておき質問に答える「エキスパートシステム」と呼ばれる人工知能が生まれ、世界中の企業で活用されて人気になる。この頃、日本においても政府主導で「第五世代コンピュータ」プロジェクトが進められた。これに多くの日本企業が参加し、日本でも人工知能の採用が隆盛を極めた。
これが「第2次人工知能ブーム」である。この時代のAI研究の中心は、主に「知識」に関するものであった。ちなみに、ニューラルネットワークにおいて、「バックプロパゲーション(逆誤差伝播)」というアルゴリズム(デビッド・ラメルハート氏ら、1986年)が使われるようになったのもこの頃である。
しかし1990年代に入ると、エキスパートシステムは知識を膨大に溜めこむ必要があり、莫大(ばくだい)なコストがかかることが明らかになった。それが限界として認識されるようになったことで、産業界への人工知能採用も下火になっていった。2回目の長い冬の時代の到来である。
4.3 第3次人工知能ブーム
2006年、その冬の時代を打ち破るきっかけとなる研究(ジェフリー・ヒントン氏ら)が発表された。これが、ニューラルネットワークの階層を深める「ディープニューラルネットワーク」という手法であり、現在の「ディープラーニング」の始まりである。
2010年以降は、コンピュータの性能や容量が大きくなり、インターネットが広く普及して膨大なビッグデータを管理できるクラウドが発展していくなど、データに関する環境が整備され高度化していった。これによって、膨大なデータを必要とするディープラーニングの研究がより容易になった。
2012年に行われた「ILSVRC」(ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition: 大規模画像認識コンテスト)で、ディープニューラルネットワークを用いた人工知能(アレックス・クリジェフスキー氏ら)が、他の人工知能の認識精度を大幅に上回った。これが、世界的な熱狂のきっかけとなった。「第3次人工知能ブーム」の始まりである。
このブームは現在も継続中だ。現在のAI研究の中心は、主に「機械学習とディープラーニング」に関するものである。この技術革新の当面の目標あるいはマイルストーンの一つとしてよく挙げられるのが「完全な自動運転」である。
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
編集部からのお知らせ