| Linux Tips | |
|
Sambaの設定をGUIで行うには 北浦訓行 |
|
Sambaの設定は、/etc/smb.conf(/etc/samba/smb.confの場合もある)を編集するのが基本だが、SWATを使用すればWebブラウザから設定できる。そのためには、SWATを使用できるようにしなければならない。
Red Hat Linux 7.xおよびTurbolinux 7の場合は、/etc/xinetd.d/swatを開いて以下の行の「=yes」を「=no」に変更する。
disable =
yes ←yesをnoに変更 |
また、Red Hat Linux 7.xの場合は/etc/xinetd.d/swatの中に、
only_from =
127.0.0.1 |
といった記述がある。これは、文字通りSWATへのアクセスを許可するIPアドレスの指定だ。これは複数記述できるので、
only_from =
127.0.0.1 |
などのようにしておく(セキュリティを考慮して、アクセスできるクライアントは絞ること)。また、デフォルトのRed Hat Linux 7.xはファイアウォール機能でSWATへのアクセスを禁止しているので、その変更も必要だ(Red Hat Linux 7.1のファイアウォール設定を変更するには参照)。
lokkitコマンドを実行して、[Customize]を選択する。そして、以下の画面で[Other ports]に[swat:tcp]と入力する。
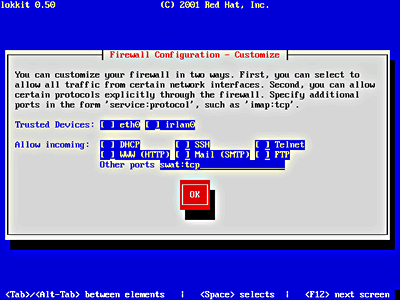 |
| lokkitによるファイアウォールのカスタマイズ |
設定が終了したら、serviceコマンドでxinetdを再起動する。
# service xinetd restart |
Vine Linux 2.xはデフォルトでSWATが使えるが、TCP Wrapperによってlocalhostからのアクセスのみに制限している。そこで、/etc/hosts.allowを変更する。
例えば、192.168.0.1〜192.168.0.254の全クライアントのアクセスを許可するには、以下のように設定する(アクセスできるクライアントは絞ること)。
swat: 192.168.0.0/255.255.255.0 |
または、以下のようにしてもいい。
swat: 192.168.0. |
/etc/hosts.allowの編集が終わったら、tcpdchkコマンドで確認するといいだろう(TCP Wrapperの設定が正しいかどうか調べるには参照)。
最後に、inetdを再起動する。
# /etc/rc.d/init.d/inet restart |
以上でSWATの設定は終了だ。Webブラウザで「http://samba:901/」(Sambaサーバの名前が「Samba」の場合)などとしてアクセスする。また、「http://192.168.0.4:901/」などのようにIPアドレスを直接入力してもいい(「http://」から入力する)。
すると、以下のようなパスワードの入力ダイアログが表示されるので、rootでログインする。
 |
| [ネットワークパスワードの入力]ダイアログボックス。ユーザー名を「root」として、パスワードにrootのパスワードを入力する |
ログインに成功すると、次のような画面になる。上部に並んだ[全体設定][共有設定]などのアイコンをクリックすると、それぞれの設定画面に進む。
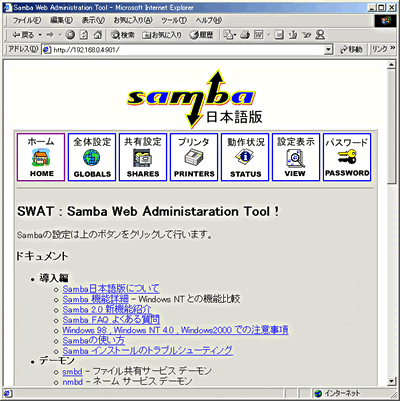 |
| SWATのトップ画面。上部のボタンをクリックすると、それぞれの設定画面が表示される |
| Linux Tips Index |
| Linux Squareフォーラム Linux Tipsカテゴリ別インデックス |
|
- 【 pidof 】コマンド――コマンド名からプロセスIDを探す (2017/7/27)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、コマンド名からプロセスIDを探す「pidof」コマンドです。 - Linuxの「ジョブコントロール」をマスターしよう (2017/7/21)
今回は、コマンドライン環境でのジョブコントロールを試してみましょう。X環境を持たないサーバ管理やリモート接続時に役立つ操作です - 【 pidstat 】コマンド――プロセスのリソース使用量を表示する (2017/7/21)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、プロセスごとのCPUの使用率やI/Oデバイスの使用状況を表示する「pidstat」コマンドです。 - 【 iostat 】コマンド――I/Oデバイスの使用状況を表示する (2017/7/20)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、I/Oデバイスの使用状況を表示する「iostat」コマンドです。
|
|




