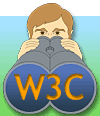
W3C/XML Watch - 7月版
MITのW3Cオフィスはもうすぐ引っ越し、
国連がebXMLを承認
2003/7/18
 |
| (写真上)写真真ん中のTというマークは地下鉄の愛称で駅の目印。駅を出るとCOOP(生協)や無線LANにアクセスできるスターバックスもある (写真中) NE43ビル近くのMIT Technology Square。手前のベージュ色のビルにW3Cが入っている (写真下)建設中のビル。外観を見るだけでも斬新でモダンアート作品のよう |
今月は、筆者が先日訪問したマサチューセッツ工科大学(MIT)のコンピュータサイエンスラボ(LCS)を紹介します。W3Cホストの1つであるMITは米国マサチューセッツ州ケンブリッジにあり、ボストンを中心に走る地下鉄のKendall駅を降りると周囲一帯がMITです。
■W3C MITオフィスの引っ越し先は、モダンアートなビル
W3Cは現時点ではMITのLCSがあるNE43ビルに入っていますが、近いうちにそばにある建設中のビルに移るそうです。
W3CのMITオフィスには約30人ほどのスタッフや関係者がいて、中には日本人もいます。現在日本からはW3C会員企業であるNECの白石展久氏が、交流プログラムの一環でW3Cフェローとして1年間W3Cに来ています。彼は技術と社会ドメインで、セマンティクスの信頼性についての技術仕様策定といった活動に参加しています。
MITオフィスは多くの小部屋に分かれており、各部屋には1人または数人のデスクが収まっています。部屋をのぞくと、多くの人が自席からテレカンファレンスをしています。白石氏は「日本ではテレカンファレンスというとまだ気構えてしまう傾向にありますが、米国では日常的で気軽に使われています。家電店に行けば多種多様なヘッドセットが販売されていることからもその浸透度が分かります。この国では市内通話は定額料金制が多く、気軽に長電話をします。そうした生活習慣からも、通信することへの敷居が低いのでしょう」と解説してくれました。
MITオフィスはネット技術を駆使した最新鋭な場所というイメージがある一方、コーヒーメーカーがある場所などは生活感のある一般的なオフィスです。各部屋はたいていドアが開いていて、声をかければすぐ応じてくれて友好的で和気あいあいとした雰囲気が印象的でした。どの部屋でも黒板やデスクを見ると技術仕様の議論や準備が進んでいる様子が熱く伝わってきました。
では、今月もW3Cが発表したXML関連の技術文書を見ていきましょう。
■6月の勧告、勧告案、勧告候補
6月の発表は勧告が4本、勧告案と勧告候補はありませんでした。
SOAP 1.2の4本が勧告になりました。これらは5月に勧告案になったばかりでしたが、すべて順調に勧告になりました。SOAP 1.2は、0部:入門、1部:メッセージングフレームワーク、2部:付属資料、アサーションズとテスト集という構成になっています。正式に勧告へと到達したことで各製品への実装が本格的に進むものと期待されています。内容については、プレスリリースも分かりやすいでしょう。
- SOAP Version 1.2 Part 0: Primer (6月24日発表)
- SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (6月24日発表)
- SOAP Version 1.2 Part 2: Adjuncts (6月24日発表)
- SOAP Version 1.2 Specification Assertions and Test Collection (6月24日発表)
■6月のドラフトとノート
ドラフトはラストコール付きが2本、それ以外が7本で合計9本です。ノートは2本です。
ラストコール付きのドラフトはDOM3が2本で、コア仕様とロード&セーブ仕様です。DOM 3はまだ開発段階ですが、現時点では勧告候補が1本(XPath)とラストコール付きが4本になりました。今回発表になったもの以外でラストコールが付いているのはイベントとバリデーションです。仕様の相関図はDocument Object Model (DOM) Activity Statementにあります。
- Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification (6月9日発表、ラストコール7月31日終了)
- Document Object Model (DOM) Level 3 Load and Save Specification (6月19日発表、ラストコール7月31日終了)
ラストコールなしのドラフトは7本あります。まずWSDL 1.2が3本です。いままではWSDLは2本立てでしたが、メインのものがPart 1、新規のメッセージパターンがPart 2、バインディングがPart 3という構成になりました。
- Web Services Description Language (WSDL) Version 1.2 Part 1: Core Language (6月11日発表)
- Web Services Description Language (WSDL) Version 1.2 Part 2: Message Patterns (6月11日発表)
- Web Services Description Language (WSDL) Version 1.2 Part 3: Bindings (6月11日発表)
| |
| |
| アクセシビリティガイドラインのロゴの例 |
ほかには音声ブラウザのCCXML 1.0、アクセシビリティガイドライン2.0、XQuery要件、World Wide Webのアーキテクチャがそれぞれ更新されました。アクセシビリティガイドラインは2.0ですが、最近はアクセシビリティガイドライン1.0に沿っていることを示すロゴマークをいくつかのサイトで見掛けるようになってきました。特に社会性の強いサイトでは重要視されています。日本では衆議院のサイトで「WCAG 1.0 WAI-A」のロゴが見られます。今回更新されたアクセシビリティガイドラインはコンテンツに関してのアクセシビリティですが、ほかにもオーサリングツールに関してのATAGというガイドラインもあります。
- Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0 (6月12日発表)
- Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (6月24日発表)
- XML Query (XQuery) Requirements (6月27日発表)
- Architecture of the World Wide Web (6月27日発表)
ノートは2本です。Webオントロジーと、UnicodeとXMLの併用についてです。後者は第7版目に当たます。今回の改訂ではUnicode 4.0に新しく追加された文字に対応したことと、マークアップ言語に適したフォーマットについての記述が更新されました。特にUnicodeとXMLの基本概念の違いといえる互換性文字について注意が喚起されています。例えば上付き/下付き文字なら、Unicodeは互換性文字を割り当てるのに対して、XMLではスタイルで指定するといった違いがあります。両者を併用するときにはこうしたことに注意をしないと障害が発生する恐れがあります。
- OWL Web Ontology Language XML Presentation Syntax (6月11日発表)
- Unicode in XML and other Markup Languages (6月13日発表)
■OASISの動き
続いては、OASISの動向の紹介です。まずは新たな協業体制の発表。OASISとロゼッタネットは6月3日に、BtoBの開発から実装までの包括的な協業体制を組むことを発表しました。この協業でOASISの相互運用性への注力と、ロゼッタネットのサプライチェーンの専門知識が互いに好影響を与えることが期待されています。
ebXMLの進展もあります。同じく6月3日にジュネーブで開催された2003年UN/CEFACT本会議総会で、最新版のebXMLが承認されたと発表がありました。UN/CEFACTは国連の国際電子商取引を取り扱う部門で、ebXMLはOASISとUN/CEFACTが中心となって開発している企業間電子商取引向けの標準仕様です。最新のebXML仕様は、ebXMLメッセージサービス仕様v2.0、ebXMLレジストリ情報モデルv2.0、ebXMLレジストリサービス仕様v2.0、ebXML コラボレーションプロトコルプロフィール&アグリーメントv2.0、ebXMLビジネス処理仕様スキーマv1.01、ebXML技術アーキテクチャv1.04、ebXML要件v1.06の7つのコンポーネントから成っています。
最後にSPML v1.0の初のお披露目です。2003年7月9日から11日までサンフランシスコで開催されたCatalyst Conference North AmericaでSPML(Service Provisioning Markup Language)のデモが行われました。SPMLは、ユーザーのアクセス権と異種の環境間のリソース情報を交換して管理するXMLベースのフレームワークです。このカンファレンスでOASISのメンバー企業が10社結集してデモを行いました。
■世界のXML標準の動き
最後に、それ以外のXML標準の話題をいくつか取り上げます。国際新聞電気通信評議会(IPTC)では、テレビ番組表向けXML言語ProgramGuideMLが承認段階に入りました。万国郵便連合(UPU)では承認済み標準S42-1「国際郵便住所コンポーネントとテンプレート」を発行しました。これは名前や住所、住所テンプレートなどが定義されていて、PATDL(Postal Address Template Description Language)というXMLフォーマットを使用しています。
OpenGISコンソーシアムではWeb Map Service (WMS) Cookbook version 1.0(PDF)が公開されました。これはOpenGISの基礎から実装と利用法までを記した初の手引書となります。WMSとは地図を扱うWebベースのソフトウェアです。また、5月末のW3Cでの特許方針の発表をうけて、OpenGISでもロイヤリティフリーの知的財産権方針を採用することを発表しています。
OTA(OpenTravel Alliance)では旅行業界の情報交換用メッセージ定義となるOTA仕様2003A版(PDF)を発行しました。このOTA仕様は120ものメンバー企業が参画して開発したXMLベースのトランザクションになります。ただ日本の旅行業界からするとOTAはパッケージ旅行商品といった日本独特の商習慣に不十分という意見が多く、今年2月末にはXMLコンソーシアムでTravelXML標準部会が発足しています。今後、OTAとTravelXMLの活動が接近するのか並行して発展するのか興味深いところです。
ではまた来月、お会いしましょう。
■バックナンバー
2001年
・ 7月版 「XMLBase、XML Linkが勧告に」
・ 8月版 「リファレンスブラウザAmaya 5.1が登場したけれど」
・ 9月版 「MITが停電! そしてマルチメディア言語SMIL」
・ 10月版 「XMLの改定仕様はブルーベリー」
・ 11月版 「W3C Dayが待ち遠しい」
・ 12月版 「慶應大学で次世代Webに触れる」
2002年
・ 1月版 「XML 1.1、XSLT 2.0のドラフトついに登場!」
・ 2月版 「Webサービスアクティビティが発足」
・ 3月版 「XMLが4歳の誕生日を迎えました」
・ 4月版 「XMLを作った人たちが殿堂入りの栄誉!」
・ 5月版 「P3Pが勧告、そして怒とうの文書公開」
・ 6月版 「XML文書の正規化新仕様と、W3Cインタロップツアー」
・ 7月版 「SOAP 1.2のドラフトが発表」
・ 8月版 「4つのXPointerのドラフト、WSDL 1.2も登場」
・ 9月版 「ロゼッタネットとUCCが合併、XMLマスターに上級資格」
・ 10月版 「具体的な技術論へ移るセマンティックWeb」
・ 11月版 「XML 1.1が勧告候補、特許問題はついに決着か」
・ 12月版 「DOM2関連がもうすぐ完結、Webアーキテクチャも登場」
2003年
・ 1月版 「この1年でW3C勧告になったのは7つの仕様」
・ 2月版 「Webサービスの『振り付けグループ』が発足」
・ 3月版 「旅行業界がXML化へ、MSからは『InfoPath』が登場」
・ 4月版 「混迷の続くXPointerはついに落着?」
・ 5月版 「Webサービスの実験成功。WS-Iからは互換性ツール」
・ 6月版 「あいまいな部分を排除したSOAP 1.2、PNGはISO標準へ」
・ 7月版 「MITのW3Cオフィスはもうすぐ引っ越し、国連がebXMLを承認」
・ 8月版 「Webサービスが日本のAmazonからも利用可能に」
・ 9月版 「IEの特許侵害判決でW3Cが緊急会合」
・ 10月版 「IEの特許侵害判決がWebに与える影響は?」
・ 11月版 「IE特許問題で、W3Cが米国特許庁へ再審査を請求」
・ 12月版 「OfficeのXMLスキーマ公開、XML 1.1は勧告間近」
2004年
・ 1月版 「セマンティックWebに向けた動きが活発に」
・ 2月版 「日本人による標準技術発信が進むOASIS」
・ 3月版 「ついにXML 1.1が勧告へ、影響を受けるのは?」
・ 4月版 「XML Schema、3年ぶりの改訂が迫る」
・ 5月版 「Webサービス・セキュリティ v1.0、待望のOASIS標準に」
・ 6月版 「TravelXMLのWebサービス実証実験デモが成功」
・ 8月版 「SOAPメッセージ最適化をめぐる仕様が活発化」
・ 10月版 「W3Cの設立10周年を祝う記念祝賀イベント開催」
・ 12月版 「年の瀬に、WebとW3Cの功績に思いを馳せる」
2005年
・ 2月版 「XMLマスター資格試験が6月にリニューアル」
・ 4月版 「WS-Security 2004の日本語訳をXMLコンソーシアムが公開」
・ 6月版 「“愛・地球博”でビュンビュンWebサービス」
・ 8月版 「XMLキー管理仕様(XKMS 2.0)が勧告に昇格」
・ 10月版 「QAフレームワーク:仕様ガイドラインが勧告に昇格」
- QAフレームワーク:仕様ガイドラインが勧告に昇格 (2005/10/21)
データベースの急速なXML対応に後押しされてか、9月に入って「XQuery」や「XPath」に関係したドラフトが一気に11本も更新された - XML勧告を記述するXMLspecとは何か (2005/10/12)
「XML 1.0勧告」はXMLspec DTDで記述され、XSLTによって生成されている。これはXMLが本当に役立っている具体的な証である - 文字符号化方式にまつわるジレンマ (2005/9/13)
文字符号化方式(UTF-8、シフトJISなど)を自動検出するには、ニワトリと卵の関係にあるジレンマを解消する仕組みが必要となる - XMLキー管理仕様(XKMS 2.0)が勧告に昇格 (2005/8/16)
セキュリティ関連のXML仕様に進展あり。また、日本発の新しいXMLソフトウェアアーキテクチャ「xfy technology」の詳細も紹介する
|
|




